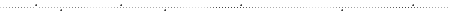平成終了記念作「きらめきに誘われて(企画小説収録)」の続編です。
リアルタイムの室青に挑戦した作品でしたが、思いの外、たくさんの方に気に入って頂きまして、支部でも好評なため、リクエストにお応えして、今度は夜の営みです。
前作と中身につながりはありませんが、リアルタイムの二人なので、年末は北海道に行って、今夏、令和の夏を迎えた設定。でもこの
設定あんま活かされてない。
07.
きらめきに誘われて 夏
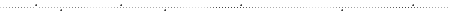
1.
太陽が照りつけ、世界がカラフルに息吹を上げた。あの角を曲がれば、そこにももう夏が来ている。
*:*:*:*:*
令和元年 盛夏。
茹だるような空気が薫風に乗り、生い茂る緑陰をわたっていた。
コンクリートを銀色に打ち返す陽射しが眩しい。
先日まで観測史上記録的な日照不足を記録した東京も、ようやく梅雨を終え、本格的な夏の訪れに蝉の声が歓びを告げていた。
ジリジリと照り付ける強さは入道雲を白く輝かせ、あちこちで祭りや花火大会といった涼夏が聞こえれば、季節はいよいよ夏本番を迎える。
令和最初の夏が、やってきた。
「なんか青空ひっさしぶり」
本庁正面玄関の脇で、青島は片手を翳して透けるような青空を見上げた。
真っ青な空がどこまでも広がり、夏の匂いが肌を奏でる。
クールビズじゃなくたってジャケットなんか羽織りたくもないこの季節に、青島はワイシャツの襟元をもう一度正して、足を向けた。
本店に来るのは年末以来だ。
あの時は室井の指示で随分とめかしこんで来たことを思い出す。
ぽんぽんと石畳を跳ねていくと、先に正面玄関から誰かが出てくるのが見えた。
青島は目を見張る。
沢山の配下を連れて黒々としたスーツを着込んだ連中の中央に凛と立つのは、室井だった。
こういう所で馴れ馴れしく話しかけたりはしない。クリスマスのアレは特別仕様だ。
腐れ縁だということは周知の事実となっているようでも、ここが国家中枢だからだ。
青島は足を戻し脇へ避け、一歩下がった。
そのまま視線も足元に落とす。
大人しく行列が過ぎ去るのを待つのが利口だ。
が、青島の前で室井の黒光りしている革の靴は動きを止めた。
「どうした」
「・・・どうしたって」
何で話しかけるんだと思いながら顔を上げると、室井は秀麗な顔を崩さず、青島の目の前で身体を向けた。
「えっと、呼び出されちゃいました」
「誰に」
「誰・・って?ぇ、そこ?・・っと、本部長さん。今うちに立ってる特捜の」
「そうなのか」
室井の目が傍目には分からないほどゆるりと細められた。
こうしてお互いの顔を見るのは久しぶりだった。
夏の陽射しに陽炎のように透けて見えた室井の気持ちに、青島は口端を持ち上げ、親指を立てる。
じゃあまたと、青島がこの場を終わらせようという素振りを見せた時、室井の漆黒の眼が僅か意味を乗せた色に移ろい、青島は小さく眉を曲げた。
その理由を告げる前に、室井は配下の者に先に行って待っているよう指示し、青島の手首を逃げ出さないように掴んでくる。
人前でこんなことをするのは室井にしては珍しい。
ましてや今は職務中だ。
びっくりして青島が自分の手元と室井の顔を二度見していると、室井はもう一度青島に向き合った。
「渡したいものがある。少し時間を取れるか」
「ぇ、ぁ、そーなの?大丈夫ですけど・・・」
「こっちだ」
今来た駐車場の方へと室井が先立つ。
引っ張られる形で、青島もその後を付いて行った。
触れるのも久しぶりだった。
警視総監となった室井に自由時間はあまり与えられず、同居も解消しているから以前より会えるチャンスは格段に減っている。
それでも現実は二人で揃って夢見てきた現実だったから、充実感ははんぱなかった。
不満はないが、寂しさも恋しさはある。
電話もしているが、やっぱり本体は違うや。
少しだけ前を歩く室井の輪郭が、残像のように青島の瞼に焼き付いてくる。
放さない室井の手に、密かに後ろでへにゃっと笑えば、青島の淡い細髪は眩しい世界にふわんと溶けた。
「あれ、今日はこっちの車なんですね」
「ああ」
いつもの室井の複数ある送迎車の裏に回る。
「実はこの下に落としてしまった。見てくれるか?」
「何を落としたって?」
「君に渡すものを、だ」
「・・ったく」
主語は抜けているから良く分からないが、青島は疑いもなくその場にしゃがみ込んだ。
と同時に室井も膝を折る。
指示をくれるのかと青島が顔を向けたその瞬間、室井は顔を傾けて青島の口を塞いだ。
「っっ!!」
しっかりと重ねられたそれは、真夏の陽射しよりも熱い。
ぬるりとした触感と共に、この距離に来て初めてわかる噎せ返るように押し寄せた室井の整髪料の香りに、眩暈すら感じて青島は目を眇めた。
薄い男の口唇は器用に動き、しっとりと青島の紅い膨らみを吸い上げ、柔らかく這い回る。
「・・・んん・・、・・っ」
思わず甘ったれた声が漏れ、マズイと思って青島が顎を引こうとした時、室井の手が青島の後頭部に回り、逃げ場を塞がれ、キスが深まる。
目の前には壮麗な瞼を伏せた室井の顔が傾けられ、影を落とす濃い睫毛が陽射しの強さに薄っすらと漆黒の瞳を覗かせていた。
肌を焼く灼けつく光線。
纏わりつく大気の湿度。
青島の眉が刺激に歪み、足元が揺らぐ。
そんな青島の変化を気付いているだろうに、室井は片膝を付いた態勢で平然と舌先で淫靡に青島の割れ目をなぞってくる。
こんな場所でどこまでしでかすか分からない男に、青島は完全に後手に回り、侵入を許した。
くちゅりと卑猥な水音が耳を何度も冒してくる。
生々しすぎてくらくらする。
ここ、本店だ。強すぎる太陽の陽射しと蝉の声。
重ねられた舌先が肉の弾力を伝え、舌の裏まで丁寧に弄ばれ、歯列まで確かめられた。
照り付ける陽射しだけじゃなくて身体が熱く、灼けるような熱が、痛い。
思わず瞼を震わせて閉じ、青島の指先は室井のスーツを縋るように掴んだ。
掻き混ぜるように室井の舌が青島の舌を絡めて、弄ぶ。
最後に唾液をこくんと飲み干して、室井は口唇を離した。
「・・・・」
室井が立ちあがり、青島のつむじを同時にくしゃりと指に絡めとる。
スローモーションのように去っていく長い指先を青島はぼうっと眺めていた。
その青島に、室井は大人びた笑みを微かに浮かべる。
「それだけだ」
言い残し、室井がこの場を去る。
颯爽とした後ろ姿に、凛とした背中が遠くなっていく。
座り込んだまま、今だに指一本動かせなかった青島は、こてんと尻もちを付いた。
「ぇ・・えぇぇ~・・っっ?」
真っ赤になった顔を隠すように両手で頭を抱え、青島は全身汗ばんでいることにも気づいた。
「もぉぉ~~~、一体どっこでこんなワザ覚えてくるんかなぁ、あのひと~」
してやられた気恥しさも今更だ。
青島はしばらくその場を動けなかった。
2.
「ちょっともぉ室井さんっ!?いる?いるよねっ!?」
扉を開けるなり、青島は大声でドタドタと足音を立てて上がり込んだ。
脱ぎ散らかしたワークブーツが背後でごつんごつんと扉を叩く。
いない筈はない。この麻布マンションのオートロックは中の者が解除しないと入室を許されない完全警備型タワマンだ。
「おかえり」
勢いよく部屋に足を踏み入れると、テーブルの脇でマカロニサラダを盛り付けしている室井が、物柔らかな笑みを浮かべて振り返った。
黒地のシックなエプロンを付け、楚々と動きながら青島を出迎える。
食卓には湯気が上がり、二人分の夕食が目に入った。
スリッパの音を微かに立てて室井が青島に近づき、青島の楽しそうに覗き込んでくる。
その光景に一気に不意打ちを食らった青島は棒立ちとなり、そう言えば何を言おうとしていたのかがすっ飛んだ。
とりあえず、考えて、考えて、今一番必要な言葉を選択する。
「・・・ぁ、ぇと、た、ただいま・・・」
室井の手が伸び、青島を柔らかく包み込んだ。
それ以上、何の言葉も付け足さない室井に、青島の両手もゆっくりと持ち上がり室井の背中をきゅっと掴む。
少しだけ背の高い青島の、丁度良い高さにある室井の肩に額を押し付け、青島はゆったりと身体の力を抜いた。
室井の腕がしっかりと青島の腰に回り、存在を確かめるように室井もまた青島の首筋に額を擦り付けてくる。
久しぶりに包まれた慣れた体温と匂いは、青島に甘い疼きを呼び覚ます。
久しぶりったって、一カ月は経っていない筈だ。
このまま抱き合っているのはまずいと思い、少し身体を離そうとするが、室井は解放してくれない。
子供を宥めるように首筋から頬へと口を滑らせ、最後に軽く青島の口唇を啄んだ。
「今日も一日ご苦労様。腹、減っているだろう?」
「・・・へってる」
「じゃあメシにしよう」
名残惜しそうに青島を放し、キッチンへと向かおうとする室井を、青島は後ろから腕を掴む。
なんだ?と振り返った室井に、同じくリップキスを返した。
「あんた、俺の扱い、うますぎ。俺、昼間のこと、もんく、言いに来たのに」
その程度のこと、分からなくてどうするとも言いたげに、室井が片眉を上げる。
「もしかして今夜俺が来ること分かってました?」
「あのキスで。・・来るように仕向けたんだ」
「!」
すっかり毒気も抜かれた青島の脱力した身体を示すように、肩からショルダーバッグまでずるりと落下した。
「早く手を洗ってこい。食べるぞ」
何年経ってもちっとも敵わない男は、エプロンを外しながらさっさとキッチンへと引っ込んでいく。
そういえば今日は本店に呼ばれたから昼を食いそこなっている。まさかそこまで見越した持て成しなんだろうか。
ただただ、青島の目が室井の後頭部を追った。
「見惚れたか?」
「!」
青島の動かない気配に気付いていた室井が、扉に手を宛がい、計算し尽くされた目線を最後に寄越す。
青島を見て微苦笑し、満足したようにキッチンへと消えたその漆黒の瞳に、何だか急速に青島の中に愛おしさが込み上げた。
悔しさ、かもしれない。
言うだけ言って、さっさと視界から消えた男を、青島は髪を右手でくしゃくしゃと混ぜてから、追いかけ
キッチンで盛り付けている室井の背中から勢いよく飛び掛かる。
「こ~ら、ひっつくな、暑苦しい」
バランスを崩しながらも青島のさせたいようにする室井に、青島は背後から肩に手を回しぎゅうっと抱き付き、額をぐりぐり擦り付けた。
「早くしてよねってね、・・・言いに来ただけ。デス」
耳朶を後ろから甘噛みして本音以外をを囁けば、室井は端正な顔を青島へと向けた。
目を細めて青島を見る視線は、口とは違って柔らかい。
「うまそう」
「食いっ逸れたいか?」
「・・・やーです」
青島は急速に空腹を思い出し、小さく笑って部屋を出た。
****
「ほら」
「ありがと。・・ゴザイマス」
夕食後、先に風呂まで済ませソファで寛いだままの青島に、頭上からマグカップが渡される。
目を細め、室井を認めてから、んっ、と青島が顎を持ち上げると、意図を察して室井が腰を曲げ、上からキスが落とされる。
風呂上がりの室井の髪から滴が青島の頬を辿った。
片手で受け取ったそれはホットココアだった。
砂糖なしの甘くないやつだ。
一口コクンと飲んで美味いと感想を呟き、青島はカップをテーブルに置くと、片手でポンポンとソファを叩く。
隣に座れという合図で、室井もそのつもりだったのだろう、返事もなく隣へ腰を下ろしてきた。
間を置かず、青島は端正な頬の下に口付ける。
「・・零れる」
「あれ?期待してたのはどちら様でしたっけ?」
あんな真昼間から、あんな場所で、あんなことして、刺激的な誘いをかけたんでしょ?
真夏の陽射しと同じ鋭い感覚が、青島の隅々までチリチリと焼き付け、今だって消えていない。
「あんなとこで、あんなことしちゃ、だめでしょ」
応えず室井はココアを啜る。
「煽ったのはそっちじゃん?責任とってよ」
諦めたように室井の手がカップを離す。
片手で青島の頤に指を掛けると、ぼってりと誘う膨らみに薄く引き締まった口唇を押し当てた。
残った手で青島の輪郭を確かめるように耳から頬へと滑らせ、室井は柔らかく吸い付いてくる。
何度も繰り返した慣れた行為。
それでもそれは飽きることなく繰り返させる。
触れるだけのキスは心地好く、青島はうっとりと瞼を落とした。
やがて室井の指先は、丹念な動きを見せ、徐々に下へと降りていく。
青島の首筋を辿り、肩へ回り、胸を撫ぜる。腕をさすり、脇を擽り、ゆっくりと指先まで来ると、絡めとるように室井の手が青島の手首を掴み――
掴んだ直後、鋭敏な動きで青島の腕はその背中へと捩じ上げられた。
同時にかかとの辺りを掬うように刈られ、重心が崩れた所で、一気にソファから横に倒される。
「うあ・・っ、あぶ・・ッ」
口唇が離れ、ソファから滑り落ちるようにずり落ちたまま、青島は室井に圧し掛かられていた。
「・・しま・・っ」
しまったと思った時には、室井が青島の首の後ろへ自分の腕を回し、抱きかかえるようにして上半身の自由を奪い
自分の顔を青島の顔に近づけるようにして、室井は上体でしっかりと抑え込んできた。
足をバタバタとさせるが、もう一向に外れない。
見事な出足払からの袈裟固めだった。基本の抑込技だが、座った低い態勢からの発動はタイミングのとり方が決め手となる高難度テクニックだ。
「割と綺麗に決まったな・・」
「なにしてくれんすか、あんた・・」
自身の胸側にある青島の腕を脇に挟み、室井は完全にロックして青島の顔を覗き込む。
キスさえ赦されそうなその距離の、その眼は心なしか艶めきを湛えていた。
「つまり、構ってほしかったんですね・・・」
「ちっとも会えなかった」
「仕方ないでしょー。あんたシゴトでしょー」
「どの口がそれを言うか」
室井の脇に捕られた腕を更にロックされ、締め付けが強くなる。
「んんッ、きゃああ~・・ぎぶぎぶだってッ!」
「まだ足りないな」
バンバンと床を鳴らす青島を他所に、にんまりと笑い、室井は返しも想定した態勢に持ち込み、得意気に見下ろしてくる。
恨めし気な青島の瞳がきらりと光った。
「くそぉぉ~、だったらこれならどうだ・・っ」
「・・ゥ・・ッ」
今度は小さく室井が呻き、身を捩る。少しだけ青島の頭を抑え込む力が抜けた。
青島が拘束されていない方の手で室井の脇腹を擽っているからだ。
ここは道場ではないのだから、なんだってありだ。
「姑息な技を・・」
「恋人の求愛タイムに無粋なことした方が反則負けですぅ~」
「生意気な口を聞くのはこの口かッ」
擽る青島の手を床に押し付け、室井が上から青島に齧り付く。
くすくす笑いながら青島も口を薄く開いて室井の下唇をはむはむと吸い付いた。
絡み合う二人の動きでラグマットがぐしゃぐしゃになっていく。
室井はこうして時々無茶なことや強引なことをして、青島に構って貰いたがった。
こんな時、青島は、逆に普段の室井の逞しさを思い、切なくなる。
警察トップに立つことになった室井には、敵はいなくなったが、代わりに室井は孤独となった。
仲間と呼べる同志たちはいるのかもしれない。腹心の部下も、いるだろう。
しかし心を許せる、全幅の安心を委ねられる相手は誰もいなくなった。
室井が悪いわけではない。組織のトップに立つということがそういうことだからだ。
今、室井が唯一心を開けて警戒を解けるのは、青島の前だけである。
それを、青島もまた、知っている。
こうして子供のじゃれ合いを仕掛けてくるくらいだから、きっとまた何か煮詰まっていたんだろう。
「はは・・っ、も、くすぐったいよ・・・」
「おまえが擽ったからだろ」
耳朶を甘噛みされ、室井の熱を孕む吐息に直に鼓膜を犯され、青島は小さく呻き、顎を反らした。
暴れたせいで少し濡れた髪の毛がその頬に張り付く。
「来た時の。訂正しろ」
「んん?話がよく?」
「名前」
「・・・ぇ、・・あ、“慎次”?」
良く出来たと褒美を与えるように、室井の指が青島の鎖骨を辿った。
電気が走り、つい青島の身体が震え応える。
それを認めてから、室井の腕が青島の頭部を囲い、角度を変えながら室井は舌で青島の輪郭を何度もなぞった。
その間に室井の足が青島の片足に絡まり、妖しい動きを見せ始め、青島はキスの端からまた甘い微苦笑を漏らしていく。
「更に何を仕掛けようとしてんですか・・・」
「バレたか」
「わっかるよ・・・何年このしかめっ面と付き合ってると思ってんの」
くぐもった青島の忍び笑いが部屋に満ち、楽し気な空気が密着する二つの身体から発せられていく。
同じボディソープの清涼感が夏の匂いが残る部屋へ仄かに放たれ、どこからか舞い込む夏虫の声が夏の夜を彩る。
組み敷かれた状態に甘んじている青島の両脚が室井の腰に巻き付き、しっかりとホールドした。
口唇から首筋へと辿り下りた室井が、青島の喉仏に甘く歯を立てる。
それすら楽しそうに笑う青島の声と、衣擦れの音は歓びのリズムで寄り添い、静かな夜が朱を乗せた嘆息を拾い上げた。
久しぶりの二人きりの夜は、穏やかで愛おしく、深まっていく。
青島が腕を軽く揺すると今度はあっさり解放され、その腕を素直に青島は室井の後頭部に回した。
くしゃりと整った室井の短髪を掻き回して強請るように囁く。
「こっちに集中してください・・・」
じっと見つめ合う。
返答はなかったが、言いたいことは十分に伝わっているし、それはきっとお互い様だ。
青島が薄っすらと瞼を伏せ、顎を持ち上げる。
はらりと落ちた室井の濡れた短髪の一房は、青島が乱したせいだ。
室井もまた吸い寄せられるように、上から口唇を重ね、滴るような甘い吐息がベッドへと誘った。
3.
オレンジ色に一つだけ灯る部屋に濃紺のベッドが海のように揺蕩う。
緩やかに室井の両腕を取った青島が、ダンスを踊るように室井を誘った。
「ねぇ、知ってます?キスって鎮静作用もあるんだって」
「なら?」
鼻が触れるほど顔を近づけ、室井が先を強請る。
腕を室井の首に回し、青島は自ら体重を後ろへと移動しベッドへと倒れ込んだ。
折り重なった二つの身体は重力のままにベッドへと縺れ込み、クッションにバウンドする。
「どうすればいい?」
「こうしてね、触れるだけ・・・」
室井の指先が愛おしさを隠しもせず、青島の髪を搔き乱しながら口唇を近づけてくる。
その薄い口唇に、青島は柔らかいリップキスを奉呈した。
「触れるだけか・・?」
「そうだよ・・唾液の交換もなし。舌も入れない。ゆっくりとね、こうやって・・・」
ぬるぬると滑る肉の弾力が、一つだけ灯したランプに薄紅に浮かび、薄く開かれる。
青島の紅く膨らむ肉を、室井は伏目となって見下ろし、押し当ててくる心地好さに付き合った。
青島の指先が室井の背中に回され、シャツを掴む。
室井は体重をかけ、その両足を絡ませた。
さわさわと衣擦れの音が水音に混じる。
「気持ちいいな・・」
「うん、俺も・・」
何があったかはお互い聞かない。
聞かなくても出来ることはあるし、伝わるものはある。
警察官を続けていれば、自ら痛みを享受し消化していかなければならないことがある。それはトップに立つほど苛酷な要求を引き連れてやってくる。
それでも俺たちは、半端な夢は語らない。
角度を変えて重ねるだけのキスに、青島は目を閉じた。
何度も何度も触れ合わせ、いつまでも触れていたくなる感触を感じ合う。
触れ合うだけで溢れた唾液が、ぬらりと青島の口許を辿った。
堪らず室井がそれを掬いあげ、そのまま深く青島の口唇を塞ぐ。
「ンッ」
「・・・つい」
「これはエロいキスですね」
「ああ」
青島の片手が室井の後頭部に回り、引き寄せる。
その瞳の中に灯る焔に、室井もまた同じ焔を宿し、その眼差しはひと時も反らせるものではなく、青島を映しこむ。
「駄目だったか?」
「・・・ぜんぜん」
「今度は、どこに?」
「俺は慎次さんのものなんだから、聞くことないでしょ。ってか、何で今日は聞くの・・?」
その言葉に、室井の漆黒の瞳に少しだけ曇りが混じった。
あ~・・・こういうことが幾つになっても室井さんって言うか、冴えないって言うか。それか、俺を愛することで何か、あったかな・・・?
グイっと青島が室井の胸倉を掴み、ちゅっとキスをする。
「言わせたい・・?言って欲しい、かな?」
「どうかな」
室井の大人びた笑みは、幾つになっても敵わない。
「んもぉ、やっぱ全然だめ!俺に集中して」
「俺を放っておいたのはどこの誰だ」
「え?それだけ?」
「引っかかる方が悪いんだ」
「くっそ~嫌な予感はしてました・・!お仕置きしてやる・・っ」
青島の両足が室井の腰に回ると、力を込めて態勢を入れ替える。
素直に組み敷かれた室井は愛おしそうに青島を見上げ、両手を挙げた。
「ああ、お仕置きしてくれ」
「苛められたいんだ?」
室井に跨ったまま、意味深に笑みを湛えた青島が見せつけるように白シャツのボタンを外しだした。
元々風呂上がりで半分ほどはだけていたそれは、青島の小麦色の肌を透かせて肌理を見せ付ける。
ゆっくりと全部のボタンを外すと、シャツは肩からするりと滑り落ちた。
勿論、視線は室井から離さない。
わざともう一度半分肩にかけ、シャツの前だけチラ見せにすると、今度はスラックスのベルトを外した。
カチャカチャという金属音が、部屋のムードに准え卑猥に響く効果音となる。
室井の視線が痛いほど肌に突き刺さっていることに、ゾクリとした。
殊更ゆっくりとチャックまで下ろしたところで、青島は動きを止めた。
「さぁて、どこから攻めようかな」
「・・早く」
嬉しそうに吐息で笑うと、青島は覆い被さり、室井の首筋をぬるりと舐め上げた。
時折歯を立て、室井が小さく息を呑むのを確認しながら、室井のワイシャツのボタンにも手を掛ける。
乗り上げた足の下で、室井の筋肉質の肉体が妖艶に身震いした。
ピクリと室井が呻いた場所を、青島は何度も舌先を尖らせ嬲り立てる。
「ここ、相変わらず、弱い・・」
「・・ァ、俊、そこばっかり・・ッ」
「だーめ、お仕置きだもん」
「・・ぅ、・・ッ、・・く、」
ピクリと室井の足が跳ね上がり、腹筋が締まる。
面白くなって、青島は何度も何度もそこを嬲る。
「俊、ァッ、・・ぅ、・・・・・てっ、・・手緩い・・ッ」
低く絞り出した声が室井から発せられたと思った途端、腹筋を使い、今度は室井が青島の腰を足で固定して捻りを加え、ベッドになぎ倒した。
「あはは、色気な~い」
楽しそうに笑う青島の両手を縫い付け、室井が馬乗りとなる。
「随分とやってくれたな」
「腰抜けちゃった?」
「今度は俺がお仕置きしてやる」
「あ~ん、お仕置きして~」
くすくすと止まらぬ笑いを零し、シャツを寛げ、自らうなじを晒して愛撫を強請ると、室井は焦らすこともなくしゃぶりついた。
容赦なく最初から性感帯を狙われ、青島の肌に紅い華が散っていく。
「うぁ、ちょ、待って待っ・・ッ」
思わず首を竦めるが、それは室井の手によって遮られた。
室井の前に無防備に晒されたうなじを、じゅるりと唾液を滴らせて室井が舌で弄ぶ。
「ちょ、ンッ、手加減・・、」
「それは心がけ次第だ」
「誰の」
「お仕置きしてって悦んだのは誰だ?」
長年かけすっかりと知られたポイントは、多くが今自分を凌辱するこの男に因って開発されたもので、執拗な刺激に青島は涙目となってもがいた。
横目で反応を確かめながら更にエスカレートする室井の玩弄に、青島の両手が室井の背中に回される。
「んっ、ンッ、ぁ、・・っ・・」
すっかりと着崩れしわしわとなったシャツの中で、汗ばんだ青島の艶肌が果実のように色付いた。
室井の腰に両脚を巻き付けるが、最早力も入らず、そのまま必死に快楽をやり過ごす。
恥ずかし気もなく、ピクンピクンと跳ねる躰も隠せない。
その嬌態に、深まって雄の色香に変わった室井の黒目が、しっとりと覗き込んだ。
「食べても、いいか」
「・・っ、は、・・はぁ・・、じゃあ、ここから先は慎次さんに任せるよ」
乱れた息の奥で囁く声色に隠微な熱が籠もり、青島の声が誘惑の兆しを乗せた。
「今日は素直だな?」
「俺はいつだって素直ですよ?」
荒い息遣いが整わないことも厭わず、青島は室井の頭に形の良い片腕を伸ばして引き寄せ、自ら口付ける。
角度を変えながら青島はその輪郭を口唇でなぞるように辿った。
堅物で、朴訥としていて、唐変木な男の激情を見届けるには、怯むつもりはない。
この男のそういう変貌を見られるのも、青島だけだから、青島にだって気合いは入る。
特に、今夜は――
甘く何度も擦り合わせ、名を囁いてみれば、合わせるように室井の薄い口唇が動き、しっとりとした熱を与えてくれる。
馴染んだ温度は同時に良く知った矯激の享楽の香りがした。
濡れた水音に混じり、ここまで戯れのようだったキスは、急速にトロリと熟した匂いに堕ちた。
昼間の灼け付くような真夏の暑さが、都会の夜を騒がせる。
遅すぎた令和の夏の夜空に、どこか近くで花火が上がっているようだった。
こうして室井と迎える夏は、何度目になるのだろう。
浅く深く、揺蕩うようにキスが水音を連れて繰り返される。
濃密な雄の本能をまだ剥き出しにはしないそれは、だが怯むことなく続けられ、追いかけるように重ねられてくる。
昼間くれたキスとは違う、その微かな刺激に、青島はどこか掴みどころがなく、その先をもっと強請らせた。
室井に抱かれるようになって、青島は淫らな自分の本性を知ってきた。けど、いつだって頭でっかちな男は、ベッドの上ですら段取りに事欠かない。
青島を喘がせるばかりで、そうすることで昂奮する性質だから、それは逆にこうやって青島の闘争心を刺激する。
「ん・・、・・・。たりない・・・」
物足りなくなって、このひととの距離をゼロにしたくて青島は必然的に持ち上げた喉元を反らした。
応えるように、室井の口唇が執拗に追ってくる。
「なんで・・・こんなにも逢いたくなるんだろうな・・・」
「一緒に生きるって決めたからでしょ」
「やっぱり、君は、模範解答だ」
室井の手が青島のシャツを捲り、身体中を弄られてその身を震わせた。
シーツを乱して二人の足が絡み合う。
完全に体重をかけられ組み敷かれた身体は、シーツとの間に拘束され、身動ぐ度に青島の艶肌を露わにしていた。
その布すら邪魔に思え、青島は室井のシャツにも手を掛け滑らせ、老いて尚美しい背中に手を這わす。
忙しなく続くキスの主導権を明け渡し、口腔を貪られながら、手の先で室井の背骨を辿り、スラックスを下げてツンと立つ尻を揉んだ。
困ったように室井の右手が青島の髪を鷲掴み、少しだけ口付けを解く。
虚ろな目で見上げた視界には、切羽詰まったような顔をした室井があった。
青島の手が室井の尻の割れ目に宛がわれ、そっと摩る。
「いつも、いいって、言ってるのに。・・・好きに、しなよ」
「君がそうやって俺を甘やかすのを知ってるから。だから――困る」
青島の視界で、平素と変わらず素っ気なく返され、眉を寄せる室井は、出会った時から変わらない。
「困っちゃうんだ?」
「まるで俺が包容力もない男になる」
「そーですよ。俺はあんたのなっさけないとこまで知ってるつもりだよ。でも、まだです。いつか別れる時にはあんたは俺に搾り取られてなーんにもなくなって
ン
の」
ほんのりとした灯りの下で、室井が微苦笑する。
その襟元を青島がぐいっと手繰り寄せた。
「俺が最後まで見届けてやる」
「――」
何かを察した室井の目が、ふと艶を帯びた。
それを認め、青島はニッと笑って見せる。
「俊。・・愛している」
「・・・んなことマジな顔で言うなよ・・・」
「冗談でなんか言えない」
「ええ、ええ、そうでしょうとも」
室井にじっと見下ろされ、黒い瞳が青島だけを映しこんだ。
「・・・・会いたかったんですから」
室井が薄く瞼を伏せ、顔を斜めに傾けキスを仕掛けた。
吸い込まれるように、青島も目を閉じて、それを待つ。
遠くでまた、花火の音がした。
馴染んだ感触も匂いも温度も、みんな青島だけに捧げられる。
何年経っても、この男に触れられる度、締め付けられるように青島の胸の奥が痛んだ。
切なげに眉を寄せ、青島はその痛みを怺るままに、室井に両手を回した。
「・・ん・・っ」
徐々にキスの速度が上がっていき、怯むことなく続く口接に、やがて青島の目尻は朱に染まり、睫毛が薄く光る。
夜光にそれが輝いた時、室井が微かに呻いた。
前触れもなく、急激に室井のキスの速度が上がる。
欲を解放した室井の、本当の姿を知るのはこんな時だ。
無防備な恋人の姿態を晒されて、青島の背筋がぞくりとなる。
いつも夕食には酒も嗜んだ。
室井は若い頃から日本酒が好きだった。
溺れるほど呑んだ姿は、見たことがない。
重ねられた口唇から洩れるまだ微かに残る香りが混じり、青島を酔わせていく。
「・・ふ・・ッ、ぅ、・・ン・・っ、・・ぁ・・っ」
やがて室井の勢いに追いつけなくなった青島の身体から力が抜けた。
覚束ない手を空に彷徨わせ、室井を求める。
やがて、酸素が持たなくなった青島が縋るように室井の腕を掴み、片膝を立てて身動いだ。
それでも室井のキスは止まらない。
「ん・・ん・・っ、」
顎を反らし、青島は室井のシャツを鷲掴む。
しかしそれでも室井の口は外れなかった。
切なげに眉を寄せる青島の顔を、伏目となって見下ろし、室井は青島の顎を固定しそのまま青島の口を割った。
太く熱い舌が注ぎ込まれ、ねっとりと絡め取られる。
途端、室井が更にキスの濃度を上げた。
「ンッ、ぅ、ふ・・・ぅ・・ッ、・・んん・・っ、」
思わず漏れ出た声に青島に押し寄せるのは、羞恥心よりも崩落感だ。
あちこち貪っていた室井の手が青島の指に絡められ、シーツに縫い付けられた。
離れがたくて、狂おしくて、青島は口を開いて室井を誘い込み、何度も舌を絡ませていく。
貪るようなキスが、青島に酩酊を呼び起こし、流され溺れていく意識を留めたくて、青島の足が何度もシーツを掻いた。
無意識に身動ぐ無防備になった身体を、室井ががっしりと封じてくる。
逃げても避けても絡め取られる舌が熱い熱に浮かされ、痺れ、感覚さえも怪しいまま、室井の遊玩にただただ翻弄されていくだけとなり
青島の舌の動きが鈍くなり、熱い舌に隅々まで蹂躙され、呻くその隙に、室井が喉奥まで侵してくる。
あっさりと反応し始めた下半身も、室井の強靭な腰に押さえ付けられ、きっともうバレている。
キスだけでこんなになる自分の変化には、この歳になっても慣れない。
そう言えば、キスで勝てたことも、なかったっけ。
ようやく与えられた刺激に青島は息もそこそこに咽び啼いた。
「ぁ・・・はっ、・・はぁ・・っ、ぁ・・・」
両手を頭上に固定され、ようやく少しだけ解放を赦された男の顔を青島は浮かされた瞳で虚ろに見上げる。
切羽詰まり、眉間に皺を寄せた室井が、同じく息を乱し至近距離で青島を見下ろしてくる。
――遠くで微かな機械音が鳴っていた。
「・・・・」
青島に馬乗りとなったまま、室井は動かない。
じっと見つめ合い、その視線を縫い付ける。
「・・・鳴ってる・・・」
「・・ああ・・」
「出なきゃ・・」
「・・・・」
動きたくない室井の気持ちは、青島には手に取るように伝わった。
もう一度名を呼ぼうと青島が瞬きをしたとき、呼び出し音は、止まった。
「慎次さん・・・」
「――分かっている」
小さく息を吐き、一度だけ躊躇うように室井の指先が強張り、諦めたように室井は身を起こした。
シャツだけを羽織り、リビングに置いたままのスマホを取りに、部屋を後にする。
オレンジの灯りに溶けるその高貴な背中を、青島は起き上がれもせずに、じっと見送った。
ドンと、また花火が上がる。
「今日花火大会なのかな・・・気付かなかった・・・」
その窓から見えるわけではないが、青島はぼんやりと薄藍に染まる窓辺へと頭を傾けた。
“どうする。止めるか?この恋を”
“喧嘩上等!相手にとって不足なしっ!”
“模範解答だな”
“ごめんね、嫌いになれなくて”
狂おしく、激しい渦に呑み込まれるように、始まった恋だった。
足元を失ったように立ち竦んだ日も、蕩けるように耽溺させられた夜も、室井と過ごせた全部が青島には鮮やかだ。
烈しく燃え盛る分、それは花火みたいに散っていくんだろうか。
室井はまだ戻ってこない。
恐らく折り返しの電話が長引いている。
住む世界が違うから、こうして青島が室井の仕事に関われないことは珍しくなかった。
その仕事内容を、室井は青島の前で零したりするようなミスは決してしなかった。
守秘義務という警察機構に於ける最重要事項のルールもそうだったが、そんなことよりも、あの約束を履行しノンキャリのままその人生を所轄に捧げた青島に
とって
上層部の情報を知ってしまうということは、そのままそれはその身の危険に直結した。
今でこそ室井と青島の仲は公然の秘密であったが、外部はそうはいかないのが現実だ。
二人が繋がっていると知った一部の悪意ある人間が、青島から情報を聞き出そうと違法な手段に出ないとも限らない。
“君はトラブルメーカーだから”
“褒めてんのね?”
“護らせてくれなんて言ったところで、どうせ聞かないだろう?”
だがそれは、青島にとっては室井の足枷となるカードでしかない。
だから素直に護られているように見える立場に今も甘んじる。事実、その通りでもあるのだろう。
時計の針を止めて。お願いだから、会えないし、向こう見ずな奴だからって俺に愛想を尽かさないで。
壊れ、崩れていくものを、手遅れと分かりつつ、掬うように幾夜も祈った。
「――俊、すまない。戻らなくてはならなくなった。おまえ、どうする?」
「ねっ、今度花火しましょうよ」
「花火?」
「だってしたことないじゃん」
「男二人で、花火・・・」
「細かいことは気にしないっ、楽しいよ~夏感じるよ~」
ベッドまで戻ってきた室井が、腰を下ろし、青島の後頭部に手を回す。
啄むようにキスをして、楽しみにしていると、囁いた。
「君のために浴衣を用意してもいいな」
「目的が違ってる・・ってか、どーしてあんたは、そう斜め上行くの?」
「やるからには中途半端はしない」
「・・・奇遇ですね。そこは――俺もです」
見つめ合う視線はもう戦闘態勢だ。
「酒、入れちゃったけど大丈夫?」
「それを口実に断ったんだがな・・・まあ、身内だけだからなんとかなるだろう」
***
着替え直し、青島は玄関へと向かう。
迎えが来ると言うことで、室井はそのまま部屋に待機することになっている。
こんな夜は、慣れっこだ。
靴を履き終え、長年愛用している三代目のショルダーバッグを肩から掛ける。
途端、背後から室井に二の腕を掴まれた。
「俊作」
「はいっ?」
振り向きざま、室井はまた青島の口唇を塞いだ。
背後から回された手が顎を持ち上げ、余韻を思い出させるような淫靡な熱が分け与えられる。
しつこいキスに、彼の名残惜しさが伝わってくる。
目を閉じて、しっとりと重ねられた熱を身体の奥にまで刻んで、青島はほうっと甘い息を零した。
「また連絡する」
「・・・はい」
すまないも、ありがとうも、ない。
別れ際は、あっさりと閉ざされる。
でもきっと、寂しさとか物足りなさは、気付かれている。