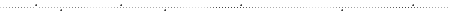14.春時雨
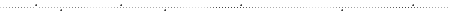
1.
湾岸署のエントランスは、鬱蒼とした木々と狭い歩道に遮られている。
吐く息さえ隠す夜、靄の向こうに浮かぶ影に抱いたのは、冬の縛りは死にも似たものだということだ。
北国から来たこの男にしてみれば当たり前のことかもしれないが
東京育ちにしてみれば、凍える大気が息吹を止める瞬間を目の当たりにすることは少ない。
「なにしてんです?」
闇の使いのような麗姿はいっそ、現実と幻覚を融合させる。
緘黙の影は、ただ静かに青島の前に立ち塞がった。
「時間、あるか」
「ない・・っつったら、拒否権あんすか?」
さあ、どうだろうかと、薄らと笑う横顔に一瞬のカーライトが赤く浮かび上がる。
彫の深さと、微塵も笑わぬ造形が、青島に般若のように見せつけた。
青島から見ても、室井はあまり喋らない男だった。
言葉少なに物事を語り、言葉足らずの不義理を敢えて好んだ。
言葉巧みに人に踏み込む青島とは、初めから真逆だ。
そして、同意なく冷酷非道なことも厭わない態度は、凡そ、万人の評価を得られるとは思えなかった。
営業で鍛えた青島にすら、数多の感情を読み取らせず、隙を見せない。
そんな男との交流が片手を超えただけで、全てを分かった気になれるほど、教えて貰えたことは少なかった。
何をしに来たのだろうと、青島があぐねていると、その闇色の視線が通りの向こうを示す。
いつからだろう、タクシーが通りを越えて止まっていた。
真っ赤なテールランプをカウントダウンのように規則正しい点滅で繰り返す。
「用件って?」
「出会ってから随分と経つな」
「・・ええ」
今更昔話をするような男ではなく、昔話に溺れるような間柄でもないため、室井の思惑が読み取れず、青島が眉を顰める。
隙間風のような濡れた冷気が鬱蒼と茂る街路樹を揺らす度、雨粒が緑陰に音を付けた。
実際、こうして向き合うのは久しぶりで、記憶の中の男とは、既に少し相違があった。
浅黒く乾いた肌は壮年の男のものだし、思ったより骨格を意識させる頬骨と尖った顎は、室井もまた一人の男であることを主張する。
こういう精悍な顔をする男だっただろうかと、青島を迷い込ませてしまうだけの時は経た。
「知らないことを覚えさせられ、気付かされ、随分と歳をとった気分だ」
こちらの心を指摘したような、要領の得ない会話に、軽い苦笑を挟みながら、何故か背筋がゾクリとした。
その理由を掴ませぬ間に、室井の声を拾っていると、室井の冷たい声は、この季節にはぴたりと寄り添う。
聞いてはいないが、冬生まれかもしれない。
その凍てつく感情のまま、青島の心に氷柱を串刺しにしてしまった。
春には早い地雨が、音なく湿らせてくる。
高潔な意志と、手折れない精神と、諦めの悪さは、生まれたての視界には魅惑的だった。
変えられることに躍起になる様はまるで学生運動の暴動のようで、今振り返る当時は世知辛い。
そんなことも知らぬ青年だったわけではないが、あの頃は何か見えない力に侵食されていた部分が確かにある。
囚われた心は留まったまま、凍り付き、時だけが過ぎていくのをただ待つのは、冬眠する野生動物さながらだ。
寝た子を起こせば、咬み付かれる。
「あれから、それなりに足掻いてもみたんだがな」
「あんたの噂話には興味ないですよ」
不意に、空気が動いた。
それまで永遠に縮まらないとすら感じていた距離を詰められ、意味を見出せぬうちに、口唇に冷たいものが押し当てられる。
「目くらい、閉じろ」
熱さえ残さず離れていった男を、ただ見つめ返した。
動揺も喜びも、怒りすら乗せない瞳に、室井もまた小さく笑む。
初めて見る顔だ。
そう思うまま、一歩も引けない足は、竦んでいるのかもしれなかった。
「いつまで経っても、君が消えないから」
「せっかちなんじゃないですか・・?」
正確に意図を読み取った青島の返しに、満足したように室井が離れた。
間に流れる空気に悔しさを残し、青島は乱暴に口唇を拭く。
「なにしに、来たの」
二度目の質問には、室井はニコリともしなかった。
いっそ、室井の方が、その鋼鉄の面の皮の裏に、熱く萌え滾る、憤怒や叱咤、悲観や情動、そういったあらゆる衝動を抑え込んでいるように見えた。
ゾクリとした正体は、たぶん、そこからだ。
「いいかげん、しんどいんだ」
春には遠い霧雨だ。細かい水滴が音もなく侵入してくる。
「終わらせたいと、思わないか?もう」
「・・あんたは、知ってんの・・終わらせ方」
「どうせなら、めちゃめちゃに壊したい」
「やっぱり、せっかちなんじゃない・・?」
せめて闇に呑まれぬようにと力を入れたせいで、反論の声は掠れた。
そんな、初心に狼狽える少年少女じゃあるまいし、どうにかする類のものだと想定していない。
恐らく、多くの大人は、抱えて生きて、薄れるのを待つ。
最初に氷柱を刺したのは、そっちじゃないか。
「付いて来い。知りたいのなら」
タクシーの赤いランプを見た時から、選択肢はきっと、なかった。
2.
初めて官舎というものの内部を見た。
一生縁がないと思っていたそこの、朽ちた扉の奥はまるで闇で、ほんの少しの冬の匂いすらも残さない。
ここに足を踏み入れることがどういう意味を持つのか、強いては、今夜の室井に付いて行くことがどういうことなのか
室井がこれからしようとしていることも、ここが最後の一線だと、全て分かっていて
分かった上で、越えた。
鋼鉄の雨に濡れた扉が、ギギと錆びた金音を上げて閉ざされた途端、口付けは始まった。
熱を持たぬ男の腕が青島の背を扉に押し付け、逃げ場を断つ。
忙しなく擦り合わせる薄い口唇はまだ僅かぎこちなさを残した。
夜気に冷えた熱を補うには不完全で、だが物足りなさを訴えるほど、親しんだ色はない。
柔らかく輪郭を辿られ、割れ目を突かれ、誘われるままに薄く口唇を開けば、目の前には闇を持つ焔があった。
「笑える余裕があるんだな」
「どんなキスするひとなのかと」
この無愛想な男の壊す接吻の行く末に幽かな興味を抱かせた。
腹ただしさを隠しもしない室井に、再び口を塞がれ、忙しなく擦り合わせる動きに、付いて行く。
女とは違う肉の厚さと、主導権を探り合う動きに、必然と口接は深くなり
やがて、熱い吐息を混ぜたそれは、熱を帯びた。
****
遠くで水音が聞こえていて、青島は四肢を惜しげもなく晒し、ぼんやりと横たわっていた。
嵐のような時間が過ぎ、先程まで自分の全てを翻弄し支配していた男は、傍らにいない。
全裸のままベッドに投げ出す身体は気怠く気重で、青島は覆い隠すことも疎ましく、天井を見上げていた。
全身に痛みがあった。
辛うじて堪えていたせいか、喉はカラカラだった。
遠くで聞こえる水音が、一層渇きを促してくる。
青島は飲み物を探そうと、ゆるりと顔を動かし、するとその動きで下肢の中央から生暖かいものが流れ落ちた。
痛みが走るそこに手を伸ばせば、どろりとした白いものが指先に付く。
ネバッとした指に流れるそれを、じっと見つめた。
男の欲望だ。
普段はデスクに向かい、或いは報道陣に向かい、あの男の指先にあるのはボードやペンやマイクだった。
テレビや会場を通して観る室井は力学さえ希薄で、どこか無機質な存在だった。
決して潔癖な理想を持っていた相手ではない。
それなりに、むしろ歳を重ねた分、そして、事件や社会を見てきた分、嵩が増し、青島よりも知識や世間を見知っていて
青島の前では見せないだけで、欲望や本能を制御していると感じていた。
それでも、このベッドに連れ込まれた先、青島のスーツを剥ぐ手付きや、肌を暴き、性感帯を探る動きは
青島の知る輪郭、偶像とはまるで乖離していた。
あの高潔な指が青島の肌を這い、的確に探り、身体の最も奥深いところまでたっぷりと濡らされていく。
室井のセックスは、殊更青島の快楽を引き出すことに専念していた。
そんな風にされたいわけではなくて、突き刺さった氷柱を一気に溶かして蒸発させるような、逆に強引に引き抜くような
そういうものを期待していた。
だが、室井はそれを許さなかった。
まるで麻酔が効かないうちは手術をしないとばかりに、全身をくまなく観察し、嬲り、気怠く手酷い愉悦を齎した。
快楽こそが免罪符とばかりに、青島の少しの変化も見過ごさず、ゆっくりと内部から熱を引き出し、愉悦を与え、肉を爛れさせた。
その官僚然とした行為が悔しくて、上がる吐息も悲鳴も噛み殺したが
それさえ完遂できたかどうかは怪しい。
荒げた息のせいで喉の奥が腫れていて、再び乾きを思い出した青島はゆっくり這い上がった。
鋭い痛みが全身に走り、軽く呻くと、内股に生暖かいものが伝い落ちていく。
出血しているようで、赤いものがシーツに染み込んだ。
自分の血液と室井の精液が交じる。
青島のナカに流れていたものが、室井の吐き出したものと交じる――それは、混ざる筈のなかった甘美と禁断の領域だ。
「それからどうするつもりだ?」
急に声が聞こえ、顔を上げた。
バスタオルを腰に巻いただけの室井が、片肘を壁に付き、寝室の入口に立っていた。
寝室などという別部屋が備わるだけでも、この官僚のための独身寮は優遇されている。
ここは室井のプライベートルームであり、知ることはないまま済む者がほとんどだ。
なのに今、そこに全身を晒す漆黒に、同じく全てを晒し自分も存在していることに、青島は噛み砕けぬ違和感を覚えた。
「そんな顔をされたら、かなり、クるんだが。無意識か」
意味が分からず小首を傾げれば、室井は妖艶に微笑んで近づいた。
頤を持ち上げられ、力で固定される。
親指で下唇をなぞられ、情婦の扱いに、強く睨み上げた。
「活きの良い獲物だ」
怒りのまま室井の親指に咬み付いた。
少しだけ室井が目を眇め、切れた指先を赤い舌で舐めとる仕草を見せ付けてくる。
同じ赤いものが自分の下肢からも流れ落ち、視覚からも青島を容赦なく追い詰めた。
風呂上がりの室井は清潔な匂いがし、先程までの汗も体液もない。
濡れた髪が室井を猛々しい男に見せ、崩れた姿態は別人のように雄の色香を放っていた。
その猛々しい姿態が青島を不安にさせる。
これは、青島の知る室井ではない。
だが、先程まで確かに自分を翻弄した雄であることは、間違いなかった。
濡れたままの肌を晒し、厚い胸板にはまだシャワーの熱と水滴が、清涼な香りを放ってくる。
「水、飲むか?」
云われ、初めてテーブルの上にペットボトルがあったことに気付いた。
ぼんやりとそれを見ていると、室井が手に取り、蓋を開け、自ら含む。
そのまま、青島の後頭部を抱え、口付けた。
流れ込んでくる潤いに、抗えない。
乾いているのはどっちなのか、まるで支配下に置き、凌辱した先程の行為を理性的に思い起こさせる男に、思わず眉を顰めた。
「つめた・・」
口端から零れ落ちた水滴を、室井が舐めとり、舌を這わせる。
喘ぐように上向く青島の視界に室井が映り込んだ。
「もっと、か?」
「・・ほしい・・」
委ねれば、何が嬉しいのか、目を眇めた室井が再び口移しで水を与えてくる。
流れ込んでくる冷たい水に、奥深いところに突き刺さったものを再現させ、こうして無防備に赦す口腔から与えられるように
無防備に懐いているうちに、氷柱は突き刺さっていた。
伝う水滴を拳で拭い、青島は舌打ちする。
「手慣れてんじゃねぇよ」
負け惜しみのように響くそれは、欲しがって乾いていたことを気付かずにいた自分の幼さだ。
室井はとっくに先まで知っていた。
「俺がいなきゃ何も出来ないのも、あんたの方だ」
「その通りだ」
やっと気付いたのかと片眉を上げる男に、言わされたことに気が付いた。
室井が欲しがっているものを、さっきまでの青島は正確には知らなかった。
氷柱が巣食う絶望的な大きさに、気付いていなかった。
「この脅威は管理できるかどうか。それを官僚は常に考える。破壊と解放は紙一重だ」
「あんたの理屈に没入体験させたいわけ」
「どうせ君はすぐ忘れる。脳の片隅に置くこともできないくせに」
それはどこか恨みごとのように聞こえた。
こちらの全てを翻弄し奪っておきながら、まだ不満を持つ男に。
こちらの氷柱を理解しようとしないで、責める男に。
感情が制御できなくて、零れ落ちる。
「胸の奥。でっかいものが突き刺さって抜けない。冷たくて、でも火傷しそうになる」
俺だって。
一人では消せない。二人でなら消せるの?
思わず漏らした合いの手は、どこか愛の告白のような響きで、間に落ちた。
「最後の晩餐には何が喰いたいか、よく話題となるだろう?」
「キャリアってしょうもないこと話してるんですね」
「逃げ出すことは赦さない。もう」
青島の中で曖昧に霞んでいた部分を浮き彫りにした。
まるでこの春時雨がじわじわと砂を流していくように、ゆっくりと、室井によってその全貌が晒されていく。
もしかしたらそれは、室井も同じだったのかもしれない。
素肌を辿られる感覚を追っていると、室井がベッドに片足を上げ、ゆっくりと体重をかけてくる。
僅かな抵抗を試みて、後ろ手に支えれば、はらりと室井の腰に巻いたタオルが外れ、その頭部からの水滴が青島の頬を濡らした。
全身を晒す室井の前で、恐らく晒すことを拒んだのは青島の方だ。
透明の、まだ何にも染まらぬ水滴に、何故か泣きたくなる。
青島が少し顔を歪めた時、室井の手が青島の腰に巻き付き、そのまま押し倒された。
「こんなの、全然、まだだ」
「必要なの」
「ふたりで、終わらせるためだ」
「これで、消せるの・・?」
フッと室井が至近距離で笑い、今夜初めて見た妖しい笑みに、思わず息を呑んだ。
見上げる室井は、男の顔で、見下ろしていた。
「消えないものを解決するのが、時の経過だけだと思うか?」
「そういう甘っちょろいの、あんたは好きじゃなさそうですね」
「ぐちゃぐちゃにしたくなる。めちゃめちゃにしてやりたくなる」
「あんた、狂ってるよ・・」
そう呟いた口唇は、また冷たいものに塞がれた。
***
「君は、消えないことに脅えないし、逃げ出さない、俺にその強さはない」
さわさわと、名残を残す肌を嬲る室井の手付きに焦りはなく、全てを明け渡す愚かな行為にも違和感を与えない。
今夜だけで見知ってしまった室井の匂いも、ソープの匂いも、身体中に記憶と共に染み付いて
噎せ返るほどの熱が、嬲られる身体に呼応していく。
それは共鳴とも違う、沼に囚われる感覚だ。
まるで慣れ親しんだ恋人同士のように這い回る指先に、必死に応えているうちに
既に物足りなさすら覚えて、青島は自ら腰を捩じった。
もう身体がこの無茶な行為を覚えたのだろう、肋骨から脇腹を舌で愛撫され、素肌を繊細な指で嬲られ
その度に敏感な青島の肌が小刻みに震え、室井を悦ばせる。
「もうこんなにしている」
何度も吸われ、朱く腫れあがった胸の尖りを、舌で弾かれ、反対側を指で捏ねてくる刺激に
吐き出す息は震えて散った。
コンクリートジャングルの中にしか存在せず、雑草とか昆虫とか季節なんか無関係の無菌室の世界で完結していそうな、物静かな男だと思っていた。
きっと、そこから勘違いなのだ。
野山を駈けずり、頑強な野生に生息するしなやかな山男のように、室井の基本はきっと、故郷だと言っていた秋田の山奥にある。
こんな原始的な策略を選ぶ男じゃないと、見誤った。
「お前のことなんて、知りたくなかった。何も知らないままでいたかった」
ゆっくりと丁寧に、少しずつ速度を上げ、見せつけるように。
春先の、まだ冷たい纏わりつくような水分がしとどに窓に打ち付ける。
夏の驟雨ともちがう、じっとりとした湿り気は、夏の温度を持たない分、リアルに熱を欲しがる欲望を意識させ
冷たく研ぎ澄まされた夜気の中で今味わうこの熱が、二人のみで生み出されたものだと錯覚させる。
背筋から肩、うなじを辿った指先が、そのまま青島の頤を捕らえ、持ち上げられ、口唇を柔らかく塞がれた。
徐々に深くなっていく口唇を受け入れる。
必然的に熱を孕み、息を上げ、それがまた同じ汗を生むことに、奇妙な安堵感さえあった。
二度目の交接はまだ緩やかで、もどかしい愛撫は、熱だけを孕み、身体を弄る指も手も舌も切ないほどの優しさを与えてくる。
きっとそれが、何を意味するのかなんて、お互い分かってない。
切なすぎる胸の痛みに、突き刺さる氷柱の凍えた痛みに、兇悪で狡猾な愛憎を知る。
圧し掛かる男の首に腕を回して、薄らを口を開放し、怯むことなく口唇を擦り合わせていく行為の合間に
教え込まれた箇所を絶え間なく愛撫され、身体が蕩けさせられた。
シーツが幾重にも波になる。
重ね合う肌にそそけ立ち、痛みさえ伴うほど過敏になってくる頃、尤も柔らかく粘性を帯びた場所を探られ
それを赦す。
湿るそこに、躊躇いなく指を咥えさせられたまま、目を開ければ焦点の合わぬ距離で室井が見下ろしていた。
室井の体液が指に股に流れ出ていく。
「ナカに、出したい」
太腿を何度も撫ぜ、迷いなく手酷い愉悦だけを巧みに引き出し、青島に与えてくる非難めいた快楽は
卑猥で甘い言葉に蕩け出していく。
息が震え、噛み締める喉が痛み、必死に怺るが、口端から散り散りになった甘ったれた声を引き出されてしまう。
視界が霞んでくる。
それが脳髄から青島を滴らせ、やがて青島の腰のあたりに抜き差しならぬ疼きを齎し
反射的に抗おうとした時、見透かしたように首筋に咬み付かれた。
「コワイか」
「こわくは・・ないかな」
こんなの、駆け引きですらない。
知りたくないと恨み言を言っていた室井は、丹念に這わせた舌で、望み通りの紅い華を青島の肌に咲かせていった。
そんな風にされたいわけではない、もうやめてくれと哀願するほどに、室井は殊更入念に悦楽を植え付ける。
先程の朦朧とした茹だるような悦楽の中で、淫らに哀願した記憶が蘇り、それが青島を脳髄から惑乱させた。
口元を抑えて横を向けば、あやすように室井が柔らかく口唇を塞いでくる。
何度も繰り返し腫れた肉を嬲られ、息を奪われ、熱に浮かされ、容赦なく引き出された快楽は脅迫のようで
青島の開かれた内股が力を失うように小刻みに震え、体重をシーツの波へと完全に預け、震えた。
「もっと、ぐずぐずにしてやる」
キスに夢中になっているうちに、明確な動きを持った指先への反応が少し遅れた。
反射的に閉じようとした青島の脚を、それより早く室井の指が遮り
今から再び男を受け入れるということを意識させるように室井が内股に熱い口唇を押し付ける。
見下ろすその目は、こうさせたのはおまえなのだと責めていた。
「ア・・ッ、・・ぁ・・っ」
吐き出す息が、夜の闇に掠れて散った。
肉を奥深くまで埋め込まれ、太く怒張したそれは、灼けるような熱さで腫れあがる肉を裂き、合わせて、まるで媚びるようにうねる。
背筋を弓なりに緊張させた青島は、絶え絶えに息を吐いた。
その背を抱えられ、衝撃に歪む青島の顔を、室井は恍惚とした表情で堪能しながら、揺さぶってくる。
余すことなく見られているという羞恥と、耐えがたい程の屈辱が、火照りを加速させ、胸板を這いまわる熱い舌戯にゆたりと首を振る。
全身の神経が剥き出しになっていて、どこもかしこも敏感に反応してしまう。
貫くまま室井が腰を回したことで、青島の身体が、シーツの上で美しく仰け反った。
滲んだ天井を見れば、室井が妖しく下唇を舐める。
熱く濡れた下唇をいやらしく舐める室井は、上品でありながらも、あまりに淫靡で
目をそらすことも出来ず引き込まれ。
「君が、絶対に欲しがらないから・・打ちのめされる」
だからぐちゃぐちゃにしたいんだと、呟かれた。
「は・・っ、あ、・・ろぃ、さ・・ッ」
思わずといった体で、青島が舌足らずに自分を凌辱する男の名を呼べば
答えはないが、気配で室井が笑んだ気がした。
先程の行為で室井が吐き出した白液が卑猥な音を立てて溢れ、内股を伝い、熱く爛れた官能の世界に落としてくる。
汗を弾く肌は、熱りを隠せず、灼けるような舌戯に男の味を知る。
逸らされた青島の喉仏が美しい彫刻を描き、戦慄く太腿が桃色に染め上がって男を挑発していた。
「ココ・・キモチイイだろう?」
ぐずぐずに蕩け始めた身体も脳内も、もう形を崩して失っていた。
叫ぶ嗚咽も悲鳴も薄く器用な口唇に飲み込まれ、耐え難い愉悦に頑是なく首を振るだけになって、すすり泣く。
不快感すら凌駕する官能的な疼きが、何度も何度も敏感な内股を擦られ、根元まで嬲られる動きから生み出され
ぬめる秘肛からあふれる蜜が、シーツに染みを描く、その作為的な動きに、思わず視界を閉じた。
最初に。
抗うことは赦されていた筈だ。
でも、朧気に霞む現実とは裏腹に、受け入れて満たされたことを知った身体が
施される愛撫に脳髄まで浸っていった。
「煙草の味がする。俺にとってあの煙草は、君の味だ」
ずり上がる身体を腰から引き寄せられ、密着した肌が汗でぬめり、狂おしいほどの熱に朦朧とさせられ
青島の手が悶えるままに室井の髪を搔き乱した。
「これが贖罪だというのなら、どこまでいけるのか、試してみたいんだ」
文学的なようで哲学的な文言も、爛れ切った脳内では快楽となる。
秋月夜みたいな静謐さもない、朧月夜みたいな灯りもない、微かな水音と湿った匂いだけが手応えもなく漏れ聞こえる室内に
衣擦れの音が混ざり合う。
「・・ァ・・ッあぁッ、・・・っ」
キモチイイんだろう?と耳元に囁かれ、素直に頷くくらいには忘我の域にあり、だが決して自我を飛ばすほど責め立ててはこないセックスは
理性と本能の狭間で、息苦しさのような昂りがこの小さな部屋の空気を早熟に燻らせていた。
魔性で純潔な恋の媚薬が酸素も毒に変える。
息を吸う度、甘さと室井の齎す毒と罪に溺れて、あやされ、満たされていく。
「俺ので、達くところ、見せろ」
脚を必要以上に両脇に押し広げ、青島の股間を眼前に惜しげもなく晒し、淫らな格好を強要させたまま
室井は特に反応の良かった場所を殊更に選び、蕩けた内部を搔き乱された。
両脚を室井に押さえられ、濡れた秘部を晒し、両手を広げてシーツを掴んで怺るが
中心部にそそり立つ自身の欲望が、脚を掲げられたせいで濡れている様子が淫らに晒される。
何かが自分の中から零れ出していく。
これが室井の欲しがったものなんだろうか。
それとも自分が望んだ形なんだろうか。
壊しに来た室井は、勇気、なんだろうか。
蕩けさせようとする初めての感覚に、閉ざしたままの心に既視感のある痛みを覚えた。
そうだ、ああ、これだ。
「俺で、ぐちゃぐちゃになれ」
ひどく淫らで甘ったれた睦言のような脅迫に、従わされて、青島の身体が軽く海老反りとなった。
吐き出す精と、仰け反る喉元に落とされる口付けの、火傷しそうな熱さが、豊かな情愛を錯覚させ
脳髄から、滴った。
―おれだけの、ものだ―
それはどちらの声だったのか。
余韻に震える腰を引き寄せられ、必然的に強くなった穿つ動きに、青島の口から熱い吐息が洩れた。
少しでも隙を見せれば、その箇所を逃さず責め立てられ、目尻から強すぎる快楽に雫が溢れていく。
神経質そうだった器用な指先で舌を弄ばれ、今まで感じたことのない得体の知れない快感に感じる恐怖も
耐え難いほどの享楽も、底のない絶望も、奥深いところを突かれる痛みも
すべて室井が与えるもので、氷柱を消滅させるには程遠く、だが蕩けるように熱い。
快楽を覚えさせられた身体中が室井から与えられる刺激に満たされている。
「・・ほらもう・・こっちはぐちゃぐちゃだ」
「ん・・っ、もっと・・っ、ぜんぶ・・っ!」
はしたない水音に容易く身体が反応を返し、揺蕩う視界に浮かぶ、自分を隈なく翻弄する男の顔に
重なる記憶と時間が、まだ慣れぬ教えられたばかりの官能の強さに青島を突き落とした。
以前はこの共鳴してしまう奇妙な感覚に捉われない様、気をつける必要があったが、もうその必要はない。
甘く蕩ける感覚に身を委ねれば良い。
何度かの啄む様な軽いキスの後、熱い息を吐いた青島の薄らと開いた口唇に
室井は自身の舌を潜り込ませ、一気に口付けを深くした。
柔らかく手酷く奪われながら、青島は自分を掻き抱く男の背中に縋る。
それでも物足りなくて、強請り、善がる。
その目尻から零れ落ちるものを、室井がすべて舐めとった。
「こんなに濡れてる・・・・・身体もこんなに熱くさせて・・・真っ赤な顔して善い声で鳴いて・・そんなに感じてるのか・・・・」
何度も頷くことで答えさせられる。
何もかも曖昧に揺らぐ薄闇に沈みながら、爛れさせる狂気染みた快楽に、それが室井から与えられたものなのか
元々己の中に潜んでいたものを引き出されたのか
その境目が分からなくなっていた。
どこかで俺も足りなくて、補うものを探し続けていた?氷柱が刺さった胸の痛みは喪失だった?
ぽっかりと無言で空いていた奥に、今満たすものを探している。
「ココ、ピクピクうねっている・・ナカで、飲み干せ」
淫らな声に唆されて、勝手に反応する自身に惑乱した。それはある種、脅迫だったのかもしれない。
儚く、脆い精神に纏わりつくような時雨が、魂の奥まで潜んでくる。
なのに研ぎ澄まされた感覚はやけに鋭敏で、もう戻れないほど遠くまで連れ込まれたことを察していた。
「あんた、は、これで、消せたの・・?」
無味無臭であることの悔しさに、青島は汗ばむ男の肌に、爪を立てた。
外はどしゃぶりになるほどの雨脚ではなく、煙雨のまま、感情を煽ることもしない分、昂る欲望が己の中にのみあったと知らしめられる。
こんなの、忘れられるわけない。身体の裡まで室井が沁み込んで、覚えさせられ、崩れて、爛れていく。
狂わされた先に忘却があるなど幻想染みたことを、室井とて考えていたわけではないだろう。
室井の中のこういう狂気を、どこかで知っていた気がした。
見つけていたからこそ、室井を見つけ出せた。歪な欠片のピースを補うように、室井を選んだ。
室井の中の混沌と渦巻く澱みは、どこか解放する術を持っていると思った。
その狂気を真正面からすべて向けられ、今、鳥肌が立つ。
「たりない・・んです」
貴方が、と青島が室井の耳元で囁きかける。
付けた痕に飾られた身体を苛めながら、執拗に舌で知り尽くした肌に室井が応えた。
口唇を重ねれば誘惑されて、滴るままに肌が薫る。
「・・・ア・・・アア・・・ッ」
舌足らずにすすり泣く声すらも、もう怺ることは止めた。
いっそ潔いほど全てを与え、潤し、赦し、知らねばならぬと思いながら、しかしその時の青島はただ、行為の意味を正確には理解していないんだろう。
悪夢のようでも、惨めでも、それでも、初めて、そんな風に、焦がれたんだ。
あやされるまま、奪われる、先程の快楽に、重なるように霞む春夜に。
頼りなく震え縋る幼子のままに、せめて春になって氷柱が溶けるまで。
この仮宿もまた、鬱蒼とした木々と狭い歩道に遮られていた。
凍雨なのか慈雨なのか。耳元に鳴り続ける音は途切れぬ罪科のようで、氷柱を溶かし奥底まで沁み込んだ。
雨はやみそうになかった。
それでもこの春雷と罪科に染まって、何もかも奪われて与えられていくままに、青島は揺蕩った。
happy end?

未発表作品
カラダだけの繋がりに落ちるふたりの悪手。室井さんから性的搾取されていく様子を青島くん視点で綴るお話。
昔こんな感じのえろ、どっかで見たよねぇ?
喘ぎ声とか、行為の描写ではなく、受側の心理描写メインでエロさを出すという作風に感銘を受け、当時、挑戦したものの撃沈
ネタ帳整理に伴い抜粋
20180502 初描
20240317 推敲