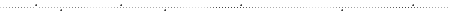11.
雨宿り
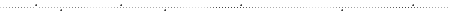
まだ仄暗く藍色に染まる部屋は時計の秒針だけが規則正しい音を奏でている。
ベッドサイドに身体を凭れさせたまま、青島は視線だけを持ち上げた。
窓の外の見慣れている筈のこの湾岸の街が、まるで他所行きの顔に見えた。
トン・・・と慣れた仕草で煙草を一本弾き出す。
その手が小刻みに震えている。
余りの自分の極限状態を思い知り、むしろ可笑しさが込み上げた。
片腕で目元を覆い、口元を苦く歪ませる。
殺したような冷笑は、嗚咽のようにも、吐息のようにも、浅葱色の朝靄に溶け、人知れず消えた。
こんな出来過ぎたホテルの一室に、何で自分はいるのか。
真冬ではない肌寒さの残るこの季節、汗ばんだ肌にシャツに袖を通しただけの身体が急速に冷やされていく。
奪われていく熱と共に、みんな消えていけばいいのにと思った。
ぼんやりと明け始めた窓から、いつかの雨の名残の向こうで、明けの明星がまんじりと覗いていた。
*:*:*:*:*
昨夜、初めて室井に抱かれた。
何であの時、室井に付いて行ってしまったんだろう。
お互いの部屋へ行き来したり宿泊するようなことは一切なかった。
青島は官舎近くで姿を見られる警戒をしたが、室井も新木場へ足を向けることを憚っていた。
お互い、部屋へ上がろうとはしなかった。
青島もそれについて強くは言及しなかった。室井も尋ねることはなかった。
二人の関係はどこまでも曖昧で、そのくせ欠けることを怖れるくらい、親密だった。
告白は室井からの結構強引な求愛だ。
それで何が変わったわけでもなく、結局逢いたがるのも、追いかけているのも、自分だけ。
一緒にいることで、このひとが少しだけでも安らげるんなら、それでいいやと割り切った。
なのに、昨夜の通り雨が、二人を皮肉に試した。
*:*:*:*:*
背後で、布の擦れる音がし、青島は室井が身体を起こしたことを感じ取った。
火も点けなかった煙草が言い訳すら奪っていることが、馬鹿らしくすら思える。
青島は指先で弄びながら、振り返ることはしない。
そっと気配が近づき、後ろから伸びた手に煙草を取り上げられた。
「吸いたいですか?」
「いつから起きていた」
「・・・・煙草」
噛み合わない会話にも、どこか今までとは違う甘すぎる余韻が、胸の奥を締め付ける。
ふわりと汗の残る髪を掻きあげられ、少しだけ室井の汗の匂いがした。
「無理をさせた。もう少し躰を・・その、休めたら、」
「オンナノコじゃないんで」
ぶっきら棒に応えた言葉は、室井の口を止めた。
ギシ・・とベッドのきしむ音がする。
細長い指先が伸び、上向かされると、そこには思ったよりも真剣な黒目がちの大きな目があり、視線を捕えられた。
室井の虹彩は、歓びよりも悲哀と悲愴の強い暗黒の闇を宿し
官僚でも警官でもない男がそこにいた。
そうだ。この目だ。
あの時、室井がこんな目をしていたから、俺は。
*:*:*:*:*
遣らずの雨は、湿度の高い空気と熱気で、スケルトンエレベーターを結露で閉ざしていた。
二人きりとなったエレベーターボックスで、腕を引き寄せられ、室井の薄い口唇が覆ってきた。
避けることは、許されていたと思うんだけど、ほんの少しの躊躇いが、反応を遅らせた。
初めて舌を割りこませ、奥深くまで粘膜を絡み合わせる、濃密なキスだった。
濡れた水音は、この中まで響く外の豪雨に混じり掻き消えていく。
それは青島が降りる直前まで続けられた。
室井の焔を宿した瞳が、姿勢良く立ち尽くしているだけの筈の躯を音もなく咆哮させ、静かに青島を見ていた。
ゆっくりとエレベーターのドアが閉まっていく。
「どうして降りなかった」
「どうしてって・・・・あんなキス、しといて・・・・」
食事をしたこのホテルから出られないほどのこの悪天候に、そのままタクシーも呼ばずにこのホテルに泊まると言いだしたのは室井だった。
気象警報が出ており、交通機関も麻痺していた。
帰れない状況はまるで運命の扉を開くようだった。
ただ、部屋は別だと、室井は言った。
「降りなかった意味が、分かっているのか」
「・・・もう少しだけ、一緒にいたら、駄目ですか・・・」
言わされた台詞だった。
解かっていただろうに、室井は青島からそう言うように仕掛けたのだ。
あれだけの濃厚なキスに答えを忍ばせて。
何も答えず、立ち尽くしたまま、二人の間を無機質な昇降音が支配する。
目的階に到着を告げる音は、覚悟の合図のように聞こえた。
その扉が音も無く滑り始めた時、室井の指が青島の指に絡まる。
逃げ場を断たれたことを感じとった。
無言で廊下を歩く。足音も聞こえない上質なマット。
誰もいない寝静まったような深閑さは現実を隔離させ、ここには外界の雨も雑音も、届かない。
カードキーでロックを解除する機械的なノイズ。
促されるままにその部屋へ足を踏み入れた。
自動でロックが掛かったと思った、その瞬間から、室井に扉に押し付けられ、激しく口唇を重ねられ、ネクタイを乱暴に引き抜かれる。
電気も点けない天井ライト一つに照らされ、息継ぎ一つさせてもらえないまま、荒々しく嬲られ、制圧される淫猥さに
もう、あの頃の俺たちじゃないことを、遠くで感じていた。
そこからはまさに、嵐のような時間で、記憶も感覚も曖昧だ。
*:*:*:*:*
「意地っ張りだな」
「知りませんでした?」
「・・・そうだな」
長い腕が背後から回り、力を込められ、憎まれ口とは裏腹に、室井が青島の髪に顔を埋めてくる。
室井が、後悔とまでは言えなくとも、少しの畏まりを感じていることが伝わった。
「・・・あんたも、寝たら?」
まだ朝は遠いから。
気を使わせちゃ、いけない。
きっと、手を染めてしまった罪を、このひとは自分一人で被る覚悟で俺を抱いた。
何てことをしてしまったのだろうか―――――目覚めて青島が真っ先に案じたのは、室井の身上だった。
室井はいずれ、警察トップにまで上り詰める男である。この国の、警備の一角を担う中枢で、最高位の地位に立つ選ばれた精鋭である。
それを信じ、期待し、サポートするのが青島の存在意義だった。
その気持ちに嘘はなかった。・・・・筈なのに。
嵐が過ぎれば、冷静さと理性が戻ってくる。
そこに初めて意中の彼に躰を与えた歓びなど、少しも入っていなかった。
どうして室井は昨日に限って抱く気になったんだろう。
例え室井に望まれても、厭われても、躯を許すべきではなかった。
近い将来、一国の機構を担う男に、何て過去を付けさせてしまったのか。
これを一生隠しきれるのか?
神聖なるものへの冒涜は、弁えているつもりだった。
大切で、宝物のように、その高潔で精高なる魂と精神を、影から護っていくつもりだった。のに。
それを、他の誰も分からなくても良い、俺だけは――俺だけは、分かっててやらなきゃいけないことだった。
*:*:*:*:*
潰されるほどの熱を込めた腕で浚うように掻き抱かれ、息を詰まらせるだけの青島に愛の常套句一つ告げもせず
ただ、雨に乱れた前髪を揺らし、室井は分厚い男の舌を捻じ込んできた。
強く引き寄せる荒々しい所作は痛いほどで、吸い上げられる舌の痛みも、奪う口唇も、密着した身体の熱に、芯から欲しがられていたことを知る。
身動げないまま、口唇を赦し、そのまま挑むように圧し掛かられ、ベッドに縫い付けられた。
縋るように見上げた室井に、鋭く灼けるような闇色の瞳で、ただ一言「貰うぞ」と、囁かれた。
悦楽の苦渋に満ちたいつもより低い掠れ声。
躯の裡から蕩けるような戦慄が走った。
促されるままに割り裂かれた花蜜は、たっぷりと濡らされ、両脚を高く掲げらて信じがたい深さまで貫かれる熱さに、声すら上げられず、咽び啼いた。
中断の言葉も、静止の嗚咽も、室井の薄い男の口唇に呑み込まれる。
シーツを掻く指先が白く力み、ただベッドを乱した。
穿たれる楔の熱さに、反り返るその喉元に野性のように噛みつかれ、闇に光る獣染みた雄の瞳が悠然と射抜いていた。
裡からどろどろに蕩けさせられ、思うように動けなくなった躯を仰け反らせると、耳元にようやく「好きだ」と熱く囁く声が一度だけ、ただ一度だけ、聞こえた
気がした。
窓に叩きつけていく大粒の雨。
荒く重なる二人の乱れた息。
毒が回るように全身を支配され、咽ぶ躯を抑えきれず、脳まで蕩けさせられた限界の先で
戦慄くような流れる雨粒と共に、仄暗い後ろめたさと微かな悦びの向こうで、ひたひたと霧散していく意識は
確かに感じていた何かをこの豪雨に流していった。
*:*:*:*:*
「水、ほしい・・・」
せり上がる感覚に、ひたすら声を堪えていたせいか、喉が酷く掠れていた。
掠れた声に、青島は自分で眉を顰める。
これじゃまるで、抱かれた余韻を呼び覚ましているみたいだ。
感じていたのが苦痛なのか快楽なのか、紙一重の豪雨に呑み込まれるままに、声を上げさせられた。
その雨はまた降り始めたようだ。
日の出前の空は白藍で、窓を打つ水滴がガラス玉のように反射している。
「青島」
呼ばれた声に振り仰げば、室井が不意に青島の顎を掴み、口付けてくる。
驚く気力もなく、受け止めさせられた。
その口に含まれていた冷たいミネラルウォーターが注ぎ込まれ、飲み干しきれないまま、青島の細長い首筋を透明の液体が流れシャツを濡らした。
喉を鳴らし、飲み干しても、室井は口唇を解放してくれない。
昨夜ほどの息も出来ないほどの獰猛さはないが、大人の仕草で、品良く口唇を邪淫した。
口腔を掻き混ぜ、下唇を甘噛みし、名残惜し気に離れていく。
ゆっくりと解放された時、瞼を上げれば、鋼鉄な瞳が青島を絡め取っていた。
自分に回る、男らしい筋肉質の腕ががっしりと躰を捕らえ、指先が首筋を撫ぜ、耳朶を掠める。
青島も、たどたどしく指を伸ばし、さっきまで自分の唾液と強淫に導かれた白濁液で濡れていた室井の口唇を、そっと指先で辿った。
この口が、ついさっきまで青島の欲望を咥え、苛烈な熱で果てさせた。
*:*:*:*:*
器用に動く舌使いに、何度哀願したか分からない。
更には自分の真上で、喜悦に頬と眦を歪ませ、室井は全身を汗で艶やかな青銅色に縁取らせて、腰を振っていた。
光も、他に何も映さない瞳に、青島だけを焼き付け、熱く律動していた瞬間は、確かに青島のものだった。
あんなに熱情的に挑まれたのは初めてで、あんなに烈しく奪われたのも、初めてだった。
返す言葉も僅かな抗いも、見透かされたように思う。
悔しさと後ろ暗さと、咽返るような背徳。
そこに混じる一欠片の仄暗い歓び。
何で。どうして。
一度も見たことがなかった、そしてスーツを纏い凛然と立つ姿からは果てなく乖離したその姿が、自分の欲望で濡れ
加減する余裕もないのか、押さえ付けたまま荒々しく腰を打ちつけてくる姿は原始の輝きを持ち
美しさが汚れる瞬間が、実はエロティシズムの究極なんじゃないかと錯覚させた。
この聖なる光を纏う、美しく清浄な魂を穢したのは俺だ。
心だけじゃなく躰も奪われたいと思ったのは、俺なんだ。
*:*:*:*:*
「後悔してるのか」
指先から全てが伝わった訳ではないだろうが、室井が不意に曖昧に弄る青島のその手を掴み取った。
こうして感情までもが、いとも容易く共振してしまう自分たちが歪だ。
こんなだから、愛なんて言う壮大な勘違いをしてしまうのだ。
青島は気付かれないように、俯いたままズルズルと躰をベッドの下に沈ませ、ぽてんとシーツに額を押し付ける。
「聞かないでくださいよ、そんなこと」
「怒ったか」
「怒れたら、良かったんでしょうけどね」
息を飲み、室井の手にきゅっと緊張が走ったのが肌で伝わる。
ただ訳も分からず、泣き出したいような衝動があった。
羽織っただけのシャツの袖から覗く青島のうなじにも二の腕にも残る朱色の刻印が、紫の大気に浮かび
身体に残る焼印は、まるで烙印のようだ。
目に入り、思わず手を引き戻す。
その手を強く引かれ捕らえられた。
ハッと見上げれば、強い視線は、それだけで鎖よりも明らかな呪縛となる。
「青島、俺は」
「言うな・・」
「言わせてくれ」
グッとせり上がるものを、青島は震えて飲み干す。
「馬鹿だ・・・」
「・・・・ああ」
俺たち、ふたりとも、大馬鹿だ。
詰まる胸を口唇を噛み締めることで、堪える。
それでも、唯一人、このひとは孤高に戦わなければならないのだと察し、愚かな自分たちの決断を、他人事のように同情した。
そうでもなきゃ、あまりに心細すぎて。
室井もベッドから降りると、青島の身体をしっとりとしたその素肌に包み込んだ。
こめかみや花瞼に口唇を落とされ、甘ったるいくすぐったさに、緩く首を振る。
だぼっと着崩れたシャツの袖から覗く手を捉えられ、抵抗を封じられた。
愛撫は愛おしさが溢れるもので、嬉しいよりも何故か切なくなった。
「泣くな・・・泣かないでくれ」
答えず、青島は昨夜は縋れなかった室井の背中に両手を回してその肩に顔を埋めた。
逞しい筋肉質の胸板が、強く、深く青島を抱き込んでくる。
「今、何を考えているのか・・・・当ててみせようか」
「・・・いい」
「ちゃんと二人で考えるから。だからいいか、暴走するなよ」
室井が青島の後頭部を掻き込み、力を込めて抱き締めた。
「ずっと、君を抱きたかった」
青島の怯弱など既に知っている口ぶりで、きっと彼はこれまでと同じように、出世レースを降りるつもりもなく
青島に未来を託すことも、何の警戒もリスクも憂慮していない。
でもそんなの詭弁だ。
それを室井は分かっていない。青島は万能じゃないのに。
ただ、室井にそうさせることを何より青島が恐れ、避けたがっていたことを、彼は察していたのだと思う。
青島が室井のために身を引いてしまうことまでも。
だからこそ、ここまで手を出せなかったのだろうと、今分かる。
「後悔なんかさせない。それだけの覚悟を持って、おまえを抱いた」
焦点が合わぬほどの距離で囁く言葉は紛れもなく睦言で
じっと見つめてくる室井の瞳は、真摯で高潔だ。
穢して尚、失わない男に、まだ何か残っているんだろうか。再び、賭けられるのだろうか。
室井が瞼を伏せ、顔を近づけた。
青島の眼差しに引き寄せられるように、ゆっくりと口唇を重ねられる。
静かに受け入れながら、青島も視界を閉ざした。
このひとを離さないでいられる未来は、きっとこんな躯の同調なんかじゃなかった。
離れたまま平気な強さが俺にもあったら、こんな結末には――。
何度も何度も口唇を重ねながら、大切だと思う気持ちも変わっていないことを室井が青島に伝えてくる。
いつしか、その想いが形を変えた。
時間をかけ、二人で過ごすプライベートの中で、徐々に、蜜やかに、歪んでいった。
気付いた時には手遅れだったのだろう。お互いに。
「・・ん・・っ、むろい、さん・・・」
怖くなって室井の首に両手を回せば、室井の腕が青島の括れた腰に回り、反り返るほど強く抱き寄せられた。
余計なことを考えるなと言わんばかりに、舌で口を割られ、キスが深くなる。
不安定な態勢を支えるために室井に縋り、口腔を貪られながら、室井の後ろ髪を搔き乱した。
室井がシャツの中に手を差し込んでくる。
一晩ですっかり慣れた無駄の無い手順で、躯を嬲られていけば、口よりも先に肌が鋭敏に震えた。
まだ微かに手が震えている。
それも、このひとには気付かれているに違いない。
「後のことは俺に任せていい」
「置いてった、くせに、今更なんだよ・・」
憎まれ口は些細な抵抗で、室井は微かに笑んだ吐息で青島の耳にキスを落とすと
青島の腰を引き寄せ、ベッドに縺れ込んだ。
室井が一気に身体を入れ替える。
ぱふんと二つの身体がスプリングに揺れた。
反動で跳ねる脚に室井の素足が絡まり、その身体をシーツに留められた。
「・・・・、一人でこんなに冷たくなりやがって・・・・」
抗おうとも、抱き返そうともしないまま、青島は圧し掛かる男を見つめ上げた。
覚束ず彷徨う腕を取られ、膝で脚を割られ、今は痕跡さえ残さず、一人冷たくなった身体に、室井が青島の両手を縫い付ける。
もう奥底まで繋がってしまったのに、尚も放さまいとする腕の必死さが、傲慢な男の性を匂わせながらもどこか子供染みていて
青島はその幼い執着のアンバランスさに、小さな苦みを浮かべた。
「何故笑う」
「だって、室井さんが男に見えて」
答えとも付かない返事に、室井もニヒルな苦笑を返し、青島の額に口付ける。
「ずっと我慢していた」
「前から俺んちとか来なかったの、・・・俺んこと、襲っちゃいそうだったから・・・?」
「ああ」
「そんなに俺、エロかった?」
「・・ああ」
「俺、あんたに、こんなことさせてまで――」
その先は聞きたくないと、室井は青島の口を強引に塞いだ。
室井の滑る薄い口唇と長い指先が、どちらも灼けるような熱を持ち、青島の素肌を、味わっていく。
ほんの一時前までは二人の体温は確かに同じだった。
同じ温度でないことさえ不満に思うくらい、室井の指先は頑固で、執拗だった。
その必死さを見れば、一気に引き出される飢えた感情がいっそ滑稽にすら思える。
フットライトと陽の光が等分に照らす室内は、淡く幻想的に浮かび上がり、閉ざされた二人だけの世界を作り
残光に輪郭を縁取られ、銀色に浮かび上がる室井の裸体は、壮絶な雄の精悍さで香り立つ。
自分の肌に熱を灯していく手のひらと口唇に翻弄され、室井が醸し出す大人の男の妖艶さと色気に、青島は強い眩暈を覚えた。
「・・・っ、ァ・・・、・・・・ッ」
胸元を嬲られ、軽く息を乱しながら、青島は横を向く。
破裂しそうな愛おしさが、照れくささを越え、室井に晒す肌が快楽を欲しがり仄かに熱を持ち始めていた。
「未開拓のこの躯が知るのは、俺だけだと思うと、たまらない・・」
室井の手が素肌を隅々まで確かめ、布も身に着けていない青島の全裸を玩弄する。
やがて、その高潔な手が茂みに沈む青島の昂りを辿った。
「・・・ん、・・ぁ・・ッ・・・」
「俺を感じてくれているのか」
「・・ぁ・・っ、ぁあ、」
「もう逃がせない」
「・・でも・・・ッ」
室井にそんなところを弄られているなんて。
羞恥で青島は内股が震え、だが閉じられない。
その動きを先に室井が足で封じ、手も押さえ付けられ、反り立つ欲望を手淫される。
さっきまでは口淫もされ、更にはもっと奥深いところで繋がり合ったというのに
こうして顔を見下ろされながら、はしたない快楽に染まっていくのは、耐え難かった。
くちゅくちゅと音を立てて昂りを上下され、まるで強請るように恥ずかしいほど勃ちあがてしまう。
求めているのは明らかだった。
室井の神経質そうな長い指先は自慰するよりも的確に快楽を拾い、青島の手が室井の後ろ髪を刺激から逃れるように強く鷲掴んだ。
その仕草に煽られるように、室井の指がボディラインを辿り降り、押し開かれた太股を辿って撫ぜあげた。
「・・ァ・・ッ、室井さん‥ッ」
哀願するも、そんな青島の仕草は室井の劣情をより煽る。
室井は口元を僅かに綻ばせるだけで、何も答えない。
内股を断続的に震わせ、踠く姿を見下ろした後、室井は再び青島の昂りを慰め始める。
くちゅり・・・。
さっきよりも熱を持ち、腫れあがったそこが更に反り返る。
堪え入るような咽ぶ声が、噛み締めた青島の口の端から漏れ落ち、夜に幾つも溶けた。
「アッ、は・・っ、ぁ、だめ、むろいさ、・・・んッ、ゃめ・・っ」
敏感な鈴口を親指で潰すように捏ね回され、青島は透明の蜜をしとどに垂らす。
くちゅくちゅと水音を立て始める青島の下半身が何度も浮き上がり、灼け付くほどの焦燥に身悶えた。
切なげに眉を寄せ、目尻を染める青島の表情に、室井の喉が上下する。
「何も分からなくなるまで、抱いてやる」
「なんでこんな・・・っ、・・ぁ・・・あ、・・・っ」
「今ならもっと、上手くやれる・・・・もっと、大事に出来る。戦う前から諦めるような男に、しないでくれ」
耳元に注ぎ込まれ、青島は汗ばんだ頬を覚束なく振り、火照らせた眦で、室井を見上げた。
濡れて艶めくその瞳に、室井が深く口を塞ぐ。
咽ぶ吐息ごと呑み込まれ、突如追い上げるように欲望を淫戯され、思わず青島は腰を震わせた。
今までないくらいの快楽を引き出してくる室井の大人びた手淫に、成すが儘に、なんとか快楽を逃がそうと青島が腰を揺すり、爪先を掻く。
もう達く・・・そう思ったその瞬間を見計らい、室井が手を離した。
なんで、と薄っすらと瞼を持ち上げれば、室井が口付けたまま青島の反応を認めており
室井の思惑通りに、快楽をコントロールされていることを知った。
「・・ぁ・・・ぁ・・・」
にこりともせず、室井は青島の瞳を見つめながら指先で茂みを辿り、今度は、その更に奥にある蜜肉を中指で回すように嬲る。
手慣れた仕草に、大人の雄を感じ、その手順で幾人の女を拓いてきたかを青島の想像させた。
反抗心は、何への嫉妬なのかも判然とせず、このまま翻弄されるのも癪だったが、四肢を囚われた躰は室井に従順で
覚束なく息を殺すしか出来ない。
焦らすような動きに、睨み上げたその時、くつり、と蜜肉に指を挿しこまれた。
くぷっと、粘性の蜜が青島の内股を伝う。
「まだ濡れてる・・・・」
意地悪に耳元に囁かれた。
ぐずぐずに蕩けたままのそこが、どんな建前よりも正直に室井へ青島の真意を伝えてしまう。
シーツに背中を預けたまま、カッと朱に染まり背けた顔を、室井が愉しそうに視姦し、無防備に晒されたうなじを舌で苛められ
卑猥な水音を立てて首筋、鎖骨と、青島の肌を舐めまわし始めた。
同じように、熟れた蜜肉に差し込んだ指で、ゆっくりと同じ水音を立てて淫蕩な動きで掻き混ぜられ、青島の内股が不規則に震えた。
「ここか・・・」
「・・・っ、ぅ、・・・ア・・ッ」
「まるで熟れた野性の美しさだ」
初めての交接では感じなかった疼きが、体内の奥底から丁寧にじわりと引き出され、室井の指に青島の躰は跳ねた。
「・・ァ・・・ッ、そこ・・、っ・・んぅ・・・ッ」
「回数を重ねていけば、もっと善くなっていく。いずれ俺のことしか考えられなくなる」
言われなくたって、膨大な悔恨の情の奥で、確かにこのひとのすべてを独占出来る喜悦を、蕩ける程に感じている。
この高潔さに、自分から触れることは出来ないと思っていただけに、肌を辿る指先一つに、青島の身体は飢えたように反応した。
これが全ての答えなのか。こんな単純で原始的なことが。
「・・ぁ・・・ッ、ゃ、も・・・くそ・・・っ」
濡れた男体が首筋を這い回り、同時に上下で粘膜にグルリと指を回され、衝撃に仰け反った青島は、喉元を室井の眼前に晒し、広げた両手でシーツを握り締め
た。
手慣れ、澱みもない室井の細長い指先の官能的な卑猥さに導かれ、緩く首を横向けるその喉元に、室井が齧り付く。
厚い胸板が重なり降りたその躯の下で、挟むように大きく開かされている太股が、小刻みに痙攣し、淫猥な仕草で幾度もシーツを掻き、雄に媚びる。
そんな指じゃ足りない。男の、硬くて太い肉に、貫かれて、埋め込まれて、奥を突き上げられた、あの感覚が欲しい。
「・・ぁああ・・・っ」
一層奥深くに突き立てられた指に、青島の意識が散在した。
何もかもが、室井の手の平の上だ。
そもそも最初から、この烈しい男に勝とうなんて、算段が間違いなのだ。
魅入られたら、毒が回るまで、喰い尽くされる。
敵わない――
なのに、室井は決定打は与えてこない。
ベッドに室井の体重で縫い付けられた躯が、過ぎる刺激に淫蕩に悶え、室井に向かって腰を揺らし、指を味わうようにヒクつかせた。
欲望を伝える先からは溢れる蜜を零す。
腫れた内壁を掻き回され、青島は顎を反らした。
「・・ぁ・・・・ッ、室・・・っ」
「付いて来い・・・ッ」
「・・・――っ」
それは、一番聞きたくて、一番言わせてはいけない言葉だった。
指を二本深く穿たれ、押し殺し損ねた息が、肺から漏れる。
仰け反り、往生際悪く逃げ道を探していた青島の視界に、嘲弄の笑みが溶け、目を瞑る。
「時間切れだ。どれだけ欲しいか、俺がどれだけ待ったか・・・思い知らせてやる」
この愛に挑むことは、即ち、破滅を意味する諸刃の剣だ。
青島の、光を散りばめた瞳に室井が映る。
室井の、闇に呑まれる深い瞳に青島が映る。
「まだ足りないか」
「・・・ァ・・・ッ、は・・・ぁ・・・っ、足りない・・・っ、全然・・・ッ。欲しいんなら、もっと本気で俺を強請れ・・・ッ」
半ば叫ぶように青島は悲鳴を上げた。
手の震えは、まだ止まらない。
「上出来だ」
輝かしい、数多の道と未来がこのひとにはあっただろうに。選べる沢山の選択肢が彼には用意されていただろうに。
それでもこのひとは俺と生きることを選ぶんだ。
この恋が、恐さを胸に秘め、また一つ室井を開花させ、一歩先の大人へと成熟させてしまったのなら
せめて、彼を立ち止まらせることだけは、したくない。
「欲しいと言え」
「地獄の果てまで連れてけよ・・・ッ」
強気な台詞とは裏腹に、身体を震わせる青島の姿が、室井の雄の本能をダイレクトに誘う。
瞳の輝きを強め、室井は今宵初めて嬉しそうな顔をした。
「んな顔しないでくださいよ・・っ」
青島の花瞼から、沢山の意味を含んだ雫が一筋の軌跡を描いてシーツに消える。
護れるだろうか。支えられるだろうか。一体、一人で、この人こそどこまで呑み込ませてしまったのか。
その覚悟を、俺は受けとめられるんだろうか。好きという曖昧な地図しか持ってない俺に。
「ったくおまえは・・本当に俺を煽る天才だ」
「俺のこと、欲しいんだろ・・ッ」
それでも引くわけにはいかなくて。
押し潰されそうな想いで言い掛けた強がりは、室井の口唇に含まれた。
後ろ髪を乱暴に引かれ、仰け反らされた口唇に、喉を鳴らし、室井がむしゃぶりつく。
突如、指も増やし、掻き回しながら強淫に刺激され、青島の目尻から強すぎる快楽の涙がこぼれた。
的確に前立腺を擦り上げる動きに、両手を抑えられたまま青島は脚を自ら大きく開き、咽び啼く。
「アアッ、あああ゛ッ、・・・ああ゛ッ、・・・・っ・・・・ッッ!!」
顎を綺麗に反らし、背中を浮き上がらせながら、青島は室井の指を咥えて白濁液を撒き散らした。
余りの強烈な快楽に、瞳を潤ませ、息が追い付かず、躰の力も入らない。
そんな青島に室井が馬乗りとなる。
男の力で抱え込まれ、両脚を裂くほどに開かされ、熟れた秘口に室井の雄々しい欲望が押し当てられた。
「ああ、ほしい」
灼けるほど怒張した肉塊が、宛がわれたそこで室井が青島の見据えた。
むろいさん、と青島が収まらぬ息の奥で口唇だけで呼ぶ。
室井が切り裂く様に青島を貫き、串刺しにされた躯が、衝撃に跳ね、悲鳴のような呻きが青島の喉から洩れた。
もうこれで、戻れない。
大切なひとを、俺が、貶めた。
自分たちの衝動だけで繋ぎ止め、愚盲な未来を選んだ。
自分がこんなことをする奴だったなんて。
同じことを言う室井が、愛しくて、憎くて、恋しい。
「・・ァッ・・、もっ・・・と・・・ッ、室・・さ・・・・・ッ」
「・・青、島・・ッ」
パンパンと肌を打つ音、惑いのない動きに合わせた卑猥な水音、二人の重なる熱い息。
今確かなのはそれだけだった。
全身に廻った毒がじわりと甘美な陶酔の時間を連れてくる。
未来に光を見てる室井と、闇しか見えない青島の、二つの影が重なり合い、紫の靄で細かい鎖が霧散していく。
汗ばんだ手で必死に筋肉質の躯を引き寄せる青島の手は、震えるままに縋り
力強い室井の手が、青島の腰を掴み引き寄せる。
同じ汗で滑り、銀色に縁取られた身体が、同じ律動に戦慄いた。
「青島ッ、青島・・ッ」
「あっ、ああ゛ッ、・・ぁあ・・っ」
このひとを、愛さないで済む未来があったなら、きっと俺には躊躇うものなど何もなかった。
変わりに、俺が俺でもなかった。
皮肉にも、神聖な物を穢す冒涜よりも、室井に置いていかれる現実の方が、俺には恐怖だった。
本当の覚悟が出来ていないのは、どちらだったのか。
共に有りたいと幼く願い、漠然とした恐怖に心許なく互いに縋り、胡乱な自分らを支えようと躯を求めた罪が
たった一度の雨で、すっかり変わってしまったように
いつか誰かの、何かの支えとなって、この決断が、せめて奇跡の始まりとなれたらいい。
そんな未来を望むことは、許されるだろうか。
今はあまりに頼りないお互いの温もりだけを、濃密な官能に堕ちながら、抱き締め合う。
手の届かない明けの明星が窓から覗いていた。
happy end

20150804