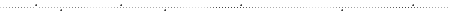登場人物はふたりだけ。擦れ違いらぶ。室井さん視点。というかほぼ室井さんの悶々とした独白。
B面とストーリーに繋がりはありません。
空騒ぎ~A面
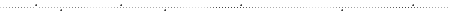
「こっち泊まるんじゃなかったのか」
「明日早いからやめとく。どうせ仕事上がりじゃキゲン悪いだろ」
「どうせって。悪くさせるのは誰だ」
室井は大きく溜息を落とした。
それさえも嫌味のように聞こえたらしく、青島が肩を竦める。
珍しくタメ口で耳に吹き込まれた言葉も、余韻もなく煙のように消えた。
煩わしいのはもう御免だと、心底思う。そんなものに費やす体力や精神力があるのなら、私は誰にも侵されることのない自分の領域を日々隅々まで整えていたい。
今日も今日とて、見目麗しい細身の背中を室井は恨みがましく見送った。
****
雨の静かな水音の合間に浮かぶ息遣いの規則正しいリズムが静謐を深めている中
室井は青島の部屋にいた。
帰ってからそのままこのソファクッションに崩れ込んだのだろう、弛緩した肉体はネクタイが解かれ、ボタンを数個外しただけで力尽きた腕を丸め
窮屈そうな眠りに落ちている。
時刻は深夜に及んでいた。
室内は、泥棒が入ったかのように散らかっている。
直前まで決めかねていた室井の足は、深夜の帰宅を六本木ではなく新木場へと向かわせていた。
自分の方からアプローチするような、そんな軟派な男だったろうか自分は。
これまで欲しいものへの努力は惜しまなかった。だが人間には然程興味はなかったように思う。
かつては無関心と達観を気取る、枯れた中年だった筈だ。
室井は脇に膝を付き、表情も変えぬまま、寝顔をじっと見下ろす。
僅かな明度に銀縁を彫る耽美な輪郭を指先で辿り、室井はゆっくりとその首筋に顔を埋めた。
華奢に浮き上がる鎖骨から際どい胸元まで、熟れた果実の如く豊潤な肉体は婀娜な香りで室井を襲う。
きっと、もうすぐ限界が来る。
黙っていれば問題ないなんて嘘だ。
「・・・すまない」
さっきは口に出せなかった言葉も、本人が眠っていればこんなにも容易く零れ落ちた。
嘘でも良いから、好きだと言わせたかった。たった一度で良いから、この熟れた甘い口唇で愛を告げられてみたかった。
親し気な笑みと、特別感、立場を越えた越権と胸を震わす騒めき。
青島にとって唯一無二になれる、職務上の共鳴にも似た法悦は、激しい飢餓を持って室井を苛んでくる。
長引かせただけ曖昧な関係は、話し合いにかけた時間さえも致命的なロスになる。
「――・・・くそ」
“ま、持っとけば”そういって手渡してくれた鍵に、どれだけの意味を期待しただろう。
結局、こうして自分の方が持て余し、青島のアパートを訪ねてしまっている。
室井は顔を埋めたまま、指先がソファを搔き毟った。
この小さなワンルームは、青島の匂いで満ちている。
自分がこんな未練たらしい男であることは、きっと、青島だって知らないのだろう。
過去を引き摺り、過去に囚われ、過去に潰される。いつも、いつもだ。
室井は甘いうなじから頭を上げ、離したくないない想いが溢れる指先で、ふっくらと銀色に濡れた口唇の輪郭を親指で辿った。
眠りから呼び覚まされつつある青島が、嫌がるように首を振る。
ドロッとした醜悪な渦にも似た体内の熱を吐き出した室井の息は重く漂い、青島のたおやかな肌を撫ぜ
その吐息に息を吹き返したように、青島の瞼が震えた。
「――」
驚いたように見開かれる宝石は、それでもまだ事態を正確に把握していない。
ぼんやりとした頼りなさで、惚けたように室井を映してきた。
覆い被さったまま、室井もまた態勢を変えず、青島の顔横に腕を付いて見下ろす。
何故室井がここにいるのか。
どうして来たのか。
説明するのも億劫だったが、青島も聞く気はないようだった。
室井が僅か顔を傾けた。
その動きに誘われるように、青島のあえかな瞼が半分伏せられる。
黒い睫毛が震え、まだ眠りの冨阪に囚われる青島に、室井は覆い被さるように口唇を重ねた。
「・・ッ・・」
締め付けられるように走った胸の痛みは、青島のものじゃない。
電気が走るような痺れに息を止め、室井は顎を捉えて逃げ場を断ち、何度も何度も口唇を擦り付ける。
敗北に似た悔しさに、つい口付けも荒くなった。
徐々に密度を増す口付けに、青島の口唇は教えた手筈でキスの濃度を高めてくる。
こんなに好きなのに。
こんなにも好きになってしまったのに。
「・・っ、は・・ぁ、は・・」
口唇を赦され、躰を赦され、更に奥まで奪いたくさせられる。
そこに青島はいない、のかもしれない。これは室井の妄想が作り出した淫らな官能の化身だ。
「・・っ、・・ンッ、なんか、あったの・・・?」
「何も」
「どけって、」
黙ったままの室井の不審な気配に少しだけ神経を尖らせ、青島が縫い付けられている両手を外そうと力を入れる。
力を力で縫い留め、合わせてソファがミシリと鳴くのを他所に、室井はまた逃げる口唇を強引に犯した。
「・・んぅ・・ッ・・」
甘い果実の様な喘ぎが、室井の舌を咥え大きく開かれる青島の口唇から溢れた。
それでも執拗に舌を絡め取り、教えたとおりに応えさせれば、二人分の唾液が闇に光る。
態勢の利も合わせ、室井に押さえ付けられて、力では敵わなかった青島が、降参したように顎を仰け反らせた。
酸素を欲するその口唇も、室井は真上から奪ってしまう。
息苦しさに愛らしい顔を歪める様が、より一層室井を急き立てた。
「・・ゃめッ、・・んぅっ・・」
両手を拘束されたまま僅かに背筋をしならせ、目尻を光らせる雫が、まるで作られた芸術のように室井の目に映った。
応えない想い人への怒りなのか、届かない感傷の苛立ちなのか。
自分でも良く分からない醜悪な愚感を見せ付けるように、室井は青島の望む箇所へは口唇を落とさず
仰け反り晒される喉仏へと舌を這わせていく。
歯でボタンを外し、愛撫を待つかのような耽美な鎖骨に舌を伸ばした。
「はっ・・ぁ、寝込み襲って楽しいかよ?イイ、ご趣味で・・・」
「そんな顔して睨んでも無駄だ」
「今日はやめたんじゃなかったの」
「ああ。もう、遊びは止めようと思ってな」
心底嫌気が差した心は、悲鳴を上げていた。もう無理なんだ。限界なんだ。
ああ、そうだ。もうこんな無意味な関係は終わらせたい。
「ヤり収めってこと」
勝ち気な眼差しが室井を裡から撃ち抜いていた。
またしても幻覚に囚われた錯覚に、室井は薄い口唇を引き、頬を痙攣させた。
誰に認められてなくても、誰に責められても、この瞳に映り込めるのなら
何だって出来た。
――だが護りきれると確信出来ないうちは、手を出すべきではなかったんだ。
もっと節度ある関係にも出来たのに、弄ばれた心根のままに彼を術中に嵌めた。
同性同士の不純な交遊など、その程度の相手に身体で番い合うほど自分は性的なことを軽く扱ってはいない。
愛に溺れて中枢を裏切るつもりもない。
自分らしくない行いは、青島に導かれた天の采配宛らに今や大きく舵を見誤った。
ここまでしたら彼は断れない。
きっと、そこまで自分は強かに計算していたんだと思う。あの時も。今も。
「ぁ、・・・ん・・っ、・・」
室井は肯定も否定もせず、嬌艶の肌に愛撫を再開する。
シャツの隙間から赤い突起が強請るように闇に浮かんだ。
そこを避けるように舌で弄べば、敏感な青島は健気に震えて息を殺す。
「ん・・っ、ん・・っ」
オトナの関係だと割り切ったつもりで、全然割り切れていないのは、こちらの方だった。
室井だけに親しさを見せ、室井だけを頼り、室井だけを信じてくれるような、そんな淡い妄想に溺れていたんだ。
「どうしてそんなに男を誘惑するんだ」
青島が反発らしきものを浮かべ、ふっと息を詰める。
刹那の呼吸で室井の勘が閃いた。
鋭く空気が震撼する。
「ン・・っ」
長い脚を折り曲げ、青島が鋼のようにバウンドした。
その狙いを先に正確に察知した室井が、空かさず腰を上げ、蹴り上げようとする隙を付き、するりとかわすと、今度は青島の反対の足が上がる。
それも室井が簡単に払い、膝蹴りをしようとする青島の先手を読み、先に内股を抑え込む。
絡み合う足と、衣擦れ。
息遣いだけが雨の音に混じる。
鋭い攻防はまるで情事のクライマックスのようにソファを鳴かせた。
両手を押さえ込まれたまま青島が腹筋を捩り、活きの良い肉体が室井の下で跳ねる。
若く手懐かない姿態を好ましく思いながら、室井はその膝を割って身体を割り込ませた。
「ぁ・・っ、うそッ、・・く・・ッ」
完全に身体の下に敷き、呆気なく支配下に置くと、室井は雄の目に変えた。
少し青島の本音に触れられた気がして、つい貪欲に耳朶を強めに噛む。
「なぁ、・・・俺のこと、本当はどう思ってる?」
脳髄に滴るような室井の思い余る白状が、妖しく夜に溶けた。
「それ、聞いちゃう?」
想いは留まることを知らず、逆上せた口唇が何度もはしたない睦言の誘いを囁いたのに
青島は熱に潤んだ透明の瞳を閉じ、室井の肩に顔を埋めるだけで
過ぎる享楽にその無垢な躯を震わせ、一度も応えてはこなかった。
届かない。
多くを知り過ぎたキャリアと違って、純潔と誠実さに囚われる彼は、穢していく度、室井だけに染め上がる。
一度でもいい。一回でも好きだと言ってくれていたら、愛を理由にこの罪に臆せず籠絡できた。
意地を張り、年上の余裕ぶって平気なフリをしてみたって、根っこのところが未完成で拗れた情愛を喚いている。
「だんまりか」
室井には似つかわしくない、歪んだ口端を持ち上げて見せ、室井は青島の首筋を長い舌でねっとりと辿らせる。
「くそ・・・ぉ」
悔しさを隠さない青島の耳朶にぴちゃりと音を忍ばせ、室井はそのまま首筋を何度も舐め上げた。
憎まれ口とは裏腹に、青島が顔を歪め、強引に与えられる快楽に怺え、悶える。
胸の尖りも苛めれば、思うように青島は身震いした。
「活きの良い魚だ」
「釣った魚・・に、餌、やんねぇくせに?」
「そうだったな、褒美だ」
両手を抑え込んだまま、室井は青島の胸の尖りを何度も何度もしつこく舌で弾く様に舐め回した。
「あっ、あっ、あっ」
ようやく与えられた直接の刺激に青島が腰を浮かせ、頭を頑是なく左右に振り、室井を挟んで開かれた足を跳ね上げる。
膝頭で股間を擦れば、青島は脚を開いたまま妖艶に跳ねた。
感度の良い躰は打ち震え、腰を揺らし、室井は踠くたびズレていくシャツと露わになっていく肌を堪能した。
「まるで娼婦だな」
「それ・・っ、で、夜這い?それともこれゴーカン?」
「どっちがいい」
荒い息遣いを浮かばせながら、青島がせめての抵抗とばかりに顔を思い切り反らす。
晒される長いうなじにゴクリと喉を鳴らし、室井が押さえ込む手に力を加えると、カクン、と、青島が身体の力を抜いた。
「意味、わかんねぇ・・・」
「分からないのはこっちなんだ」
「本気で言ってる?」
「本気を見せないおまえがそれを言うとは滑稽だ」
「回りくどいね、不満があるならはっきり言えばいいだろ、別れたいとか、捨てたいとか!」
強気の視線が、それでも勝ち気に室井をきつく睨み上げてきた。
徐々に精気と覇気を取り戻し爛漫となる美しい瞳は、室井が焦がれ惑わされた原点だ。
毒そのものと言っていい。
それだけで室井の理屈めいた思考は全て吹っ飛ぶほど、どうでも良くなってしまう。
こんなに夢中にさせられて、過去だけの繋がりになるなんて、あんまりだ。
誰よりも大切だと、拙い言葉で本音を告げ、青島も頷いてくれたのに
絶対離さないからと何度も言い聞かせたのに
届かない。
どこまで奪っても一歩下がり、快楽に追い詰めた恍惚に濡れても、青島は黙ったまま顔を埋めるだけだ。
全てを奪った筈だった。なのに青島は遠い存在だった。指先から擦り抜ける。零れ落ちる。恋人と呼ぶには頼りない、細いつながりだ。
恋と呼ぶにはあまりにも爛れで、愛と呼ぶにはあまりにも自分たちは幼稚だった。
俺が悪かったんだろうか。
それとも、俺が弱かったんだろうか。
「認めるんだな」
何故こんなに儚いのだろう。
純潔な青島が応える筈もなかった。分かっていた結末だった。
「こんな夜に来てしたい話ってそれなんだ?は・・っ、くっだんねぇ」
興味も失せたような青島の横顔に、ただ痛む心が共鳴する。
こんな処ばかり通じ合ったって、意味がない。本当のところが掴めないまま、指先から零れる彼を繋ぎ止める術を知る筈もなく
あまりに絶望的なところまできてしまった距離に、室井は改めて眉間を深めて俯いた。
そろそろ効果を失っていた室井の前髪が、敗北を受け入れるがの如くハラリと額を打つ。
「終わらせたいのはいつだって室井さんでしょ」
まるで正反対の苦情を向けられ、いっそ可笑しくすらなった。
甘い口唇に口付けをした。熟した躯に埋め込んだ。一途な恋に不満も後悔もないのに。
「俺に言わせようだなんて、甘いんだよ」
「そうだな、残酷だ」
「どっちが!」
「俺は君が好きなんだぞ!」
「俺だって好きだった!」
間髪入れずに言い返しあい、同時に二人は目を見開いて至近距離で見つめ合った。
煽られ、思わず感情を爆発させてしまった室井は、だがそのことよりも青島の言葉に思考が停止する。
目の前に焦がれてやまない飴色の瞳が冥い深淵に煌めく。
官能的でさえあるその瞳に恨みごとを乗せる挑発に、室井は息を止めるしかなかった。
「?」
室井の虚を突かれた顔の青島が、変な顔に変わる。
お互いに想定外の答えだったらしいことを伝える沈黙は、無情な静謐を呼んだ。
「・・・」
「・・・」
どちらも次の言葉を繰り出せずに出方を窺う。
この状況は、いっそ頭を抱えたい。
どうやら本気で伝わっていなかったらしい室井の鈍感さに、こんな所だけ遠慮がちな青島の純情が
二人の拗れた白痴に陋劣を知る。
加えて、青島は今何と言った?本気か?
青島は片眉を顰め、困ったような、拗ねたような、曖昧な顔で戸惑いを見せた。
「だが・・・おまえ、」
ようやく絞り出した室井の言葉も、みっともなく尻切れとなる。
言葉を選べと教わったのは遥か昔警察学校だったか。どうでも良いような回想が室井の混乱を表している。
まだ半信半疑のような顔で室井を見上げ、先に青島が確信の目に変えた。
「どして今更そんなこと言うんだよ・・」
「・・・」
「あんたと生きていくんだよ」
「・・・」
青島が怒っている理由は、やっぱり室井の悩みとは全く違う処にあった。
きっと、一生噛み合わない。
でも、青島が自らの意思で、俺を選んでいる。
「こんなに純情晒してんのに、なんでわかんねーかな?俺、・・っ」
室井は言葉もなく口唇を押し当てていた。
呼吸も止めるキスを都合も考えず重ね、頭を捕え、ソファに沈み込んだ二つの身体が絡み合い、折り重なる。
強引に奪った口唇の弾力を潰すように擦り合わせ、痛いくらいに過敏となった皮膚が性感を高めるまま、口を封じた。
まだ触れちゃ駄目だ。
肝心なことを聞いていない。
分かっているのに、止まれない。
「・・・あんなことまでして・・・、アソビに見えました?なに今更?」
助けてくれと、自分の心の奥が泣き叫んでいたことを、ここで室井は初めて感じ取った。
壊れそうで、崩れそうで、もう俺は泣き出したかったんだ。
「それじゃ、だめなの?」
だけど、こんな時青島はいとも容易く室井を掬い上げる。いつだって。
「だめ、ではない」
「それだけ?」
青島が両手を室井の首に回し、脚を絡ませてきた。
咽ぶように咆哮の喉を鳴らし、室井は息継ぎのタイミングさえもどかしく、角度を変えて舌を捻じ込ませる。
薄く開いた青島の歯列を割って、顎を反らすことで舞う青島の細髪を鷲掴み、奥深くまでの肉の淫らさに、確かに馴染んだ自分のものだと確認する。
消えていく残像を追い求めるかのように、何度も何度も口唇を粗雑に擦り合わせて、離れてはまた押し付け、烈しく舌を絡ませる。
「・・ッ、ん、も、苦し・・っ」
「君は、私を慰める天才だ」
「ぇ、イっちゃった?」
きょとんとした顔で青島が室井の股間に膝を充てた。
その膝に、自ら腰を揺すり擦り付けながら、室井は熱を帯び始めた雄を青島に伝える。
青島の両手を頭上で纏め、しなやかに伸びる肢体に狂い、雄の声で囁いた。
「襲ってもいいか」
「いいけど・・」
「縛ってもいいか」
「・・・ヘンタイですね」
「手錠があった」
「犯罪者?」
きっと、手放したら青島は自由になれるんだろう。
それが分かっていて尚、手に入れたい兇悪な執着を知る。
どうしても手放せなかった。離れられなかった。
青島の手をぎゅっと握る室井の顔色が変わる。
「青島」
「は、ははい・・っ?」
「もう一度言ってくれ」
強くきつく腕に囲み、頬を両手で押さえ、額を押し付けた室井が灼けつき掠れた声で哀願する。
「は?なにイイ歳して恥ずかしいコト強請ってんですか?」
しばらくの沈黙も、室井はただ静かに待ち続けた。
ゆっくりと、青島の長く美しい四肢が室井に優雅に纏わりつく。
汗ばんだ額を掻き揚げ頬にキスを落とせば、青島の指先が室井のシャツをきゅっと引き寄せた。
「むろいさん」
「ああ」
「むろいさん・・」
「ああ」
愛おしくて狂おしくて、懇願する瞳と腕の強さに根負けした青島が、なんの抵抗もためらいも乗せない、無垢な瞳で見つめ
やがて薄っすらと閉じ、室井の耳に口唇を寄せてくる。
「貴方が、すきです」
少し掠れた、熱を帯びた声。
室井は心臓が弾け飛んだ。
それすらも確信犯のようで、青島の真剣な眼差しが室井を嫋やかに挑発してくる。
少し赤らんだようにも見える目尻、真摯な眼差し、扇情的で、だが青島も少し照れていることが窺えた。
見下ろしたまま固まれば、魅入る間に濡れた睫毛が軽く伏せられ、青島が首を延ばして、今度は室井の口唇に神聖にキスをした。
いつも、一生懸命だった、健気だった。
なんで懐いてくるんだ。無邪気だった。
不思議だった。
この恋は、障害や邪魔なんかじゃない――言い聞かせた所でその意味を一番知っているのはむしろ室井の方なのだ。
「今頃知ったの・・?」
青島の澄んだ瞳が室井を見上げ、愛し気な色を湛えて、泣きそうに歪んだ。
「すまなかった」
気障な指先で室井は、青島の頤を持ち上げ、囁いた。
その大人びた仕草に、青島の方が息を呑んで視線を彷徨わせる。小さく漏れる苦笑い。
狼狽えるその心に付け込み、今度こそ彼を捕まえる。
「そんなことより言うことあんでしょ」
彼もまた、少しは俺にドキドキしてくれているんだろうか。
あんなに焦らして虐めて、それでも聞けなかった言葉は、こんなにも容易く零れ落ち、こんなにもあっさりと室井を満たした。
どこまで奪わせれば気が済むのか、どこまで狂わされてしまうのか。
キスを仕掛けようとした室井の口唇を、青島の手が堰き止める。
「ここで逃がすとか、ないでしょ」
青島は、純潔だけど室井にはない柔軟性がある。
キスもセックスも、室井の仕込みを覚え、期待以上の成果で驚かす。
青島が身体だけの関係だなんて割り切るほど、冷めた奴ではなかった。
「釣った魚には餌をやらないと、だったな」
「そうですよ」
青島が室井の首に両手を回し、瞼を伏せながらキスを仕掛けてくる。
あっさりと火が点く身体に呆れながら、室井は愛らしい顔だけを目に映し、口唇を重ねてやった。
嬉しそうに微笑む青島が、何度もキスを強請ってくる。
だから、あれだけ言えなかった言葉が、ようやく室井の口からも零れおちる。
「そばにいてくれ」
ここまで追い詰められないと言えないなんて、捨てられてもおかしくなかった。
「頼む。そばに、いてほしい」
しょうがないなというように、青島が室井の口唇を啄む。
「ねぇ、お揃いの指輪ほしいなって俺が言ったらどうする?」
「そういうものを君が欲しがるとは意外だ。バレたくないのかと」
「だってトクベツって感じじゃん」
「・・・」
「相手さえ分からなきゃいいんですよ」
青島が室井の指に紅い舌を這わす妖艶な顔に、室井は強張った顔で唸った。
かわいい顔して大胆なことを言ってくる悪魔は、勝ち気に笑う。
「勝手に誤解して俺を捨てようとしたお詫び、もらってないよ」
「朝まで啜り啼かせてやる」
罪深い情熱に身を焦がし、瑞々しく広がる未知の感情に、自分は脅えていたのかもしれない。
まだ底知れぬ自分を暴き出されて、行儀の良い言い訳も通用しなくなり、本気でぶつかるしかなくなった。
これでは室井は敗北感しかない。
どうやら思っていたより悪ガキだったらしい相棒は、共に堕ちる恋人としても申し分ない男だった。
happy end

室井さんは一人で悶々と拗らせるタイプ。そしてプッツンきちゃうひと。
20210916